現在掲載中の企業73件
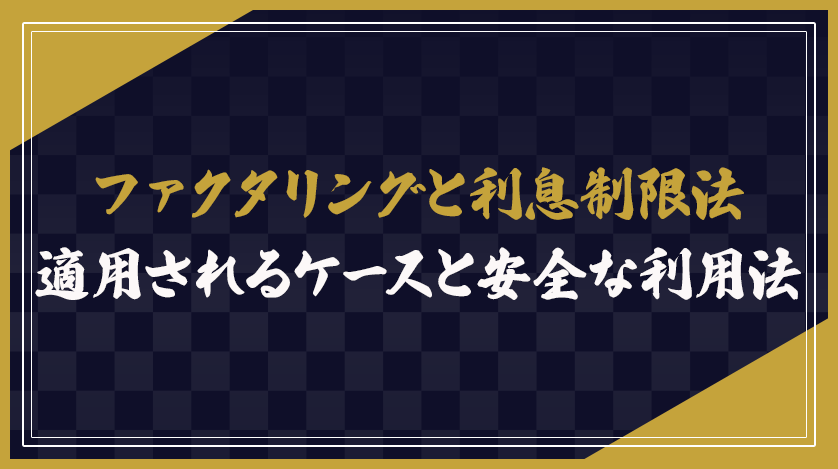
ファクタリングは、経営資金の調達手段として注目度が上がっています。とはいえ、利息制限法との関係性について、多くの経営者が不安を抱えているでしょう。
本記事では、利息制限法の適用の有無を判断するポイントと、安全にファクタリングを利用するための具体的な方法を解説します。中小企業の経営者が知っておくべき重要な情報を分かりやすく説明していきましょう。

ファクタリングは利息制限法に関係があるのか、多くの経営者が気になるところでしょう。一見複雑に見える制度面も、基本を押さえれば理解しやすくなります。ファクタリングと利息制限法の関係性について、具体的に見ていきましょう。
ファクタリングは、企業が保有する売掛金や請求書を買い取る金融サービスです。資金繰りに困った際、売掛金を現金化できる仕組みとして広く活用されています。
通常の借入とは異なり、債権売買という形を取るため、返済義務は発生しません。融資ではなく債権を売却する取引となります。
売掛金を早期に現金化できる利点から、特に中小企業や個人事業主に人気があります。支払期日までの期間に応じた手数料が発生しますが、信用調査(与信審査)は融資より緩やかな場合が多いでしょう。

利息制限法は、貸金業者からの借入における金利の上限を定めた法律です。年利15-20%という上限を超えた契約は無効となり、超過分は返還請求が可能となります。
金銭消費貸借契約(融資契約)が対象で、債権売買など他の形態の金融取引には原則として適用されません。ただし、形式的に債権売買であっても、実態として貸付と同様の性質を持つ場合は利息制限法の規制対象となるでしょう。
ファクタリングは基本的に売掛債権の売買取引であり、利息制限法の適用対象外です。債権の所有権が完全に移転し、返済義務も生じないためです。
手数料は利息とは異なる性質を持ちます。利息が元本使用の対価であるのに対し、ファクタリング手数料は債権買取りのサービス対価という位置づけになります。
法律上は債権譲渡として扱われ、民法上の売買契約に該当します。
債権の所有権移転を伴う正当な取引として認識されているのです。
ただし一部の取引形態では、実質的な貸付として判断される可能性があります。形式的な契約内容だけでなく、取引の実態に基づいて判断されます。

ファクタリングは、いくつかの要素が重なると利息制限法の適用対象となるリスクが高まります。経営判断を誤らないよう、具体的なケースを詳しく確認していきましょう。
買戻特約とは、売掛先からの入金がない場合に、利用者が債権を買い戻す義務を負う契約条項です。実質的には返済義務と同様の効果をもたらすため、貸付としての性質が強まります。
買戻特約では、支払遅延や債務不履行時に債権の買戻しを強制されます。債権の所有権移転が完全でなく、リスクが利用者に残る形となるのです。
このような契約は実質的な担保付き貸付として判断される可能性が高くなります。債権売買の形式を取りながら、実態として金銭消費貸借に近い性質を持つためです。
過去には買戻特約付きファクタリングが金銭消費貸借契約にあたり、違反とされた判例も存在します。
契約内容の確認は慎重に行う必要があります。
売掛金以外の財産を担保として設定するケースも要注意です。不動産や預金口座など、追加の担保設定がある場合は貸付としての性質が強まります。
具体例としては、工場や店舗などの不動産に抵当権を設定するケース、経営者の個人資産に担保権を設定するケースなどが挙げられます。
このような取引形態は、債権売買という本来の姿から逸脱し、担保付き融資に近い性質を帯びます。金融庁の実質判断基準に照らして問題視される可能性があるでしょう。
担保設定を求められた場合は、取引の本質的な性格を見極める必要があります。必要以上の担保提供は避けるべきです。
給与債権を対象とするファクタリングは、特に注意が必要です。個人の給与債権取引は貸金業法上の規制対象となる可能性が高いためです。
給与債権は性質上、個人の生活費に直結します。そのため法律による保護が厚く、取引に制限が課されています。
金融庁は給与ファクタリングを実質的な貸付として判断する傾向が強く、利息制限法の適用対象となるリスクが高まります。それどころか、利息制限法だけでなく、貸金業登録がされていなければ貸金業法違反にもあたるのです。
手数料が著しく高額で、実質的に貸付行為と判断される場合、手数料が利息制限法の利息上限を超えると取締の対象になることがあります。
実質金利の計算には、手数料総額を融資額と期間で割り戻す方法が用いられます。年利換算で20%を超える場合は要注意です。
利息制限法の上限金利(年15-20%)を超える手数料設定は、たとえ債権売買の形式を取っていても違法と判断されるリスクがあります。
一般的なファクタリング手数料は売掛金額の1-30%程度とされています。極端に高い手数料を請求される場合は、取引を再検討すべきでしょう。

安全にファクタリングを活用するために、契約時の確認事項と利用上の注意点を解説します。リスク回避のポイントを押さえることで、より安全な資金調達が可能になるでしょう。
契約書の細部まで確認することは、安全な取引の第一歩です。買戻特約の有無、担保の設定、手数料の計算方法など重要な条件を見落とさないようにしましょう。
金銭消費貸借とみなされ、利息制限法が適用される可能性のある買戻特約が設定されていないか、まず確認が必要です。
担保設定に関する条項も注意深く確認しましょう。売掛金以外の資産への担保設定の要求は、取引の性質を変えるリスクがあります。
適切なファクタリングを選ぶことは、安全な取引の重要な要素です。給与ファクタリングは避け、事業者向けの合法的なファクタリングを選びましょう。個人向け取引は規制リスクが高く、事業資金調達には適していません。
業者を選ぶ際は複数社から見積もりを取得し、取引条件を比較検討するのがおすすめです。極端に有利な条件を提示する業者には警戒しましょう。
また、利用手数料が適正範囲内に収まっているか確認することも大切です。
取引開始前に法律の専門家への相談を検討しましょう。弁護士や司法書士、行政機関など、金融取引に詳しい専門家のアドバイスは有益です。
事前確認事項としては、契約書の内容確認や手数料計算方法の妥当性の判断などが挙げられます。専門的な観点からのチェックで見落としを防げるでしょう。
問題が発生した場合は、すぐに専門家や監督機関に相談することをお勧めします。早期対応が被害の拡大を防ぐ鍵となります。
各地の弁護士会や消費者センターなど、相談窓口は積極的に活用しましょう。無料相談から対応できる機関も多く存在します。
ファクタリングは事業資金調達の有効な手段ですが、利息制限法との関係には注意が必要です。基本的に債権売買取引として利息制限法の適用外となりますが、取引形態によっては規制対象となるリスクがあります。安全な取引のため、契約内容の確認を徹底し、必要に応じて専門家に相談しましょう。正しい知識と適切な判断で、ファクタリングを経営に活かすことが可能です。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。