現在掲載中の企業73件
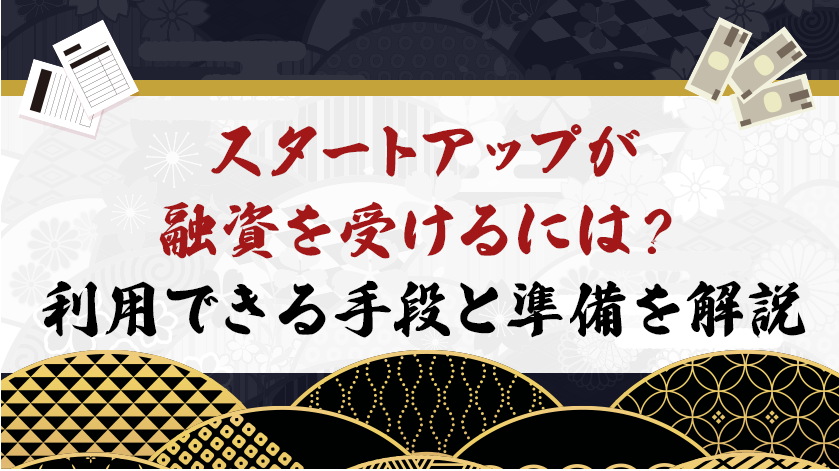
スタートアップ経営者の多くは、資金調達の壁にぶつかることがほとんどです。
銀行融資や政府系金融機関からの借入れなど、選択肢は多岐にわたりますが、実際に融資を受けるには、周到な準備と適切な事業計画が不可欠です。
近年では、様々な融資制度や支援プログラムが整備され、スタートアップ経営者にとって資金調達の門戸は確実に広がっています。そこで本記事では、スタートアップ経営者向けに融資を受けるための具体的な方法と準備について解説します。

スタートアップ企業がベンチャー企業として成長するまでの道のりで、資金調達は避けて通れない課題です。特に事業拡大期における運転資金の確保は、経営者にとって最重要事項と言えるでしょう。しかし、融資による資金調達は、返済能力の証明や事業計画の提示が求められます。金融機関からの信頼を得るため、経営者には十分な準備が求められます。また、融資実行後の資金管理と返済計画についても、入念な検討が必要です。
創業期は売上が安定せず、固定費負担が重くのしかかる時期です。
人材採用や設備投資、商品開発など、成長に必要な投資ができず、機会損失を招くリスクも発生してしまうでしょう。また、資金不足は、事業の成長速度を鈍化させるだけでなく、最悪の場合、事業継続自体を危うくする可能性も秘めています。
そのため、事業拡大期は運転資金の確保が特に重要です。
なぜなら、売掛金の回収までタイムラグが生じる一方で、仕入れや人件費は先行して発生するためです。この資金繰りギャップを埋めるには、計画的な資金調達が欠かせません。
資金調達を成功させるには、綿密な事業計画書(ビジネスプラン)が必要不可欠です。
事業計画書では、市場分析に基づく売上予測と、具体的な収益モデルを明示することが求められます。金融機関は、事業の将来性と返済能力を重視して審査を行います。計画書作成時には、業界動向や競合分析、顧客ニーズの把握など、多角的な視点からの検討が必要です。
また、資金繰り計画も重要な準備項目の1つです。月次での資金の入出金を可視化し、返済原資を確保できる見通しを示さなければなりません。さらに、資金使途は可能な限り明確にし、調達額の妥当性を説明できる状態にしておきましょう。
主な融資先としては、大きく分けて民間金融機関と政府系金融機関による融資があります。
民間金融機関では、都市銀行や地方銀行、信用金庫などが代表的です。担保や保証人が必要となるケースが多く、創業間もない企業には審査のハードルが高くなります。一方で、取引実績を積み重ねることができれば、長期的な関係構築が可能になるでしょう。
次に、政府系金融機関である日本政策金融公庫は、創業支援に力を入れています。
創業前や創業後間もない企業向けの融資制度が充実しており、比較的審査基準が緩やかです。無担保・無保証人での融資も可能な制度があり、経営指導や事業計画策定の支援なども受けられる点が特徴です。
民間プログラムでは、ベンチャーキャピタル(VC)による出資や、クラウドファンディングなど、新しい形態の資金調達手段も登場しています。
融資型クラウドファンディングは、一般投資家から小口の資金を募る仕組みで、事業内容次第では有効な選択肢です。

日本政策金融公庫(日公庫)では、創業時の資金不足を支援する目的で設けられた融資制度を実施しています。民間金融機関と比べて利用しやすい条件が特徴です。
「新規開業資金」と「中小企業経営力強化資金」という二つの主要な融資を中心に、創業支援の取り組みを展開しています。
新規開業資金は、創業時に必要な設備資金や運転資金を調達できる制度です。
担保や保証人について柔軟な相談が可能で、創業直後でも利用できる点が特徴となります。設備資金については最大7,200万円まで、運転資金は4,800万円までの融資を受けることができます。創業期特有の資金需要に対応した制度設計と言えるでしょう。
また、返済期間は設備資金が20年以内、運転資金が7年以内と、長期的な返済計画を立てられる点も魅力です。事業が軌道に乗るまでの期間を考慮しつつ、柔軟な返済スケジュールを組むことが可能となります。さらに、据置期間を設定することで、創業直後の返済負担を軽減させることも可能です。
中小企業経営力強化資金は、新事業分野への進出や事業の多角化を図る際に活用できる融資制度です。
既存事業の強化や新規事業の立ち上げなど、事業の発展段階に応じた資金需要に対応します。経営革新計画の承認を受けた企業は、優遇金利での融資を受けられる場合もあります。事業の革新性や成長性が評価されるポイントです。
融資限度額は、中小企業事業で7億2,000万円、国民生活事業で7,200万円となっています。資金使途は幅広く、設備投資や研究開発費用、人材採用費用なども対象です。経営力強化に向けた積極的な投資を支援する制度として、多くの企業に活用されています。
新規開業資金の利用には、いくつかの条件を満たさなければなりません。
新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内という期間要件があります。また、 具体的な事業計画書と一定額の自己資金を準備することも求められます。自己資金は、総事業費の10%以上が目安です。
さらに、 代表者の信用情報も審査の重要な判断材料となります。過去の借入返済履歴、金融機関からの借入経験がない場合は、クレジットカードの利用履歴なども参考にされます。

スタートアップ経営者が融資を受ける際は、審査時のポイントを押さえ、融資実行後の資金管理まで見据えた準備が必要です。以下では、注意点や資金計画について解説します。
融資審査では、返済能力が重視されます。収益モデルが実現する可能性や、資金計画の妥当性が詳細に検討されるため、あらかじめ準備しておかねばなりません。
また、売上予測は、市場分析や競合状況を踏まえた現実的な数字である必要があります。過度に楽観的な計画は、審査で厳しい評価を受ける可能性が高くなるため注意しましょう。
なお、金融機関は経営者自身のリスク負担を重視するため、必要以上に大きな融資額を申請すると、返済リスクが高いと判断される可能性もあります。
資金使途と必要額を明確に示し、適正な融資額を申請するようにしてください。
融資を受けた後は、資金の使途を明確に管理する必要があります。
事業計画に沿った支出管理と、返済原資の確保が重要です。支出項目を細かく分類し、予算との差異を定期的にチェックする体制を整えましょう。
また、返済スケジュールは、事業収支を考慮して綿密に立てる必要があります。月々の返済額が事業に過度な負担とならないよう、余裕を持った計画が望ましいです。特に季節変動や業界特性による売上の波についても、しっかりと考慮しましょう。
事業の成長段階に応じて、段階的な資金調達を検討しましょう。必要な時期に必要な額だけを調達する方針が、リスク管理の観点から望ましいとされています。成長のスピードと資金需要を見極めながら、適切なタイミングでの資金調達を心がけてください。
なお、過度な借入れは返済負担を重くし、成長の足かせとなる可能性があります。成長投資と返済負担のバランスを見極めた資金計画の立案が、事業が成功する上で必要不可欠です。
スタートアップの資金調達では、事業段階に応じた適切な融資制度の選択が重要です。
特に日本政策金融公庫によるスタートアップ融資は、創業期の資金需要に応える有効な選択肢となります。融資を受けるための準備を怠らず、事業計画と資金計画を綿密に立てることで、円滑な資金調達を目指しましょう。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。