現在掲載中の企業73件
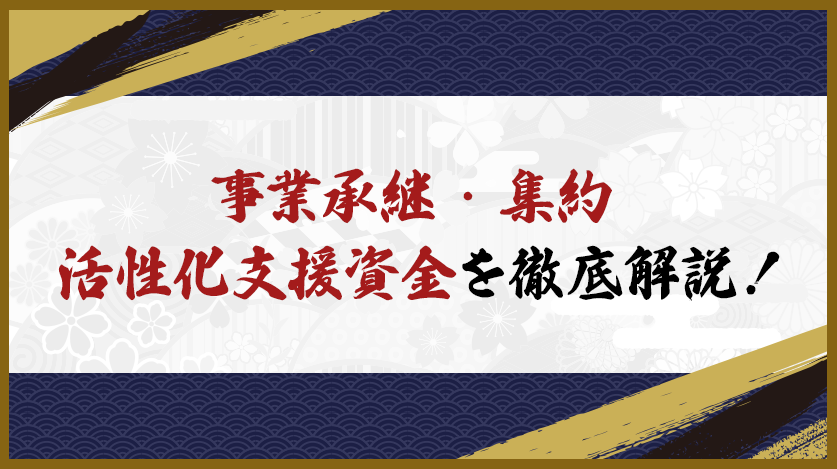
経営者にとって避けて通れないのが、事業承継の問題ではないでしょうか?
日本政策金融公庫では「事業承継・集約・活性化支援資金制度」を通じ、中小企業における事業承継の円滑な実現に向けた支援を実施しています。今回は、事業承継計画の策定から実行までを支援する本制度について、申込条件や審査のポイントなどについて解説します。

事業承継問題に直面する中小企業経営者に向け、日本政策金融公庫では充実した支援メニューを用意しています。この融資制度を利用することで、設備投資や運転資金といった事業承継に必要な資金を調達できます。事業承継計画に基づく着実な実行を金融面から後押しする本制度について、詳しく見ていきましょう。
日本における、中小企業の後継者不足は深刻度を増しています。経済産業省の調査によると、70歳以上の経営者のうち実に半数以上が後継者未定の状態です。
経営者の高齢化が進む一方で、事業承継の準備が整わないまま廃業に追い込まれるケースが後を絶ちません。地域経済の担い手である中小企業が消滅することは、雇用機会の損失や技術・ノウハウの消失にも直結します。
事業承継問題は中小企業の課題を超え、日本経済全体に影響を及ぼす社会問題となっています。
日本政策金融公庫が提供する「事業承継・集約・活性化支援資金」は、中小企業における円滑な事業承継実現を目的としています。
事業承継やM&Aなどに伴う資金需要に対応し、設備投資から運転資金まで幅広い用途での利用が可能です。
融資限度額は、事業承継の資金需要に応じて個別に設定されるものの、一般的には最大7,200万円(運転資金を含む) が目安とされています。返済期間は設備資金で20年以内(うち措置期間5年以内)、運転資金で10年以内(うち措置期間5年以内)となっています。金利は事業規模や返済期間によって、個別に設定されます。
本制度における事業承継の形態は多岐にわたります。親族内承継では、経営者の子息や親族への事業承継が対象となります。
従業員承継など親族外承継も支援対象です。長年企業に貢献してきた従業員が経営を引き継ぐケースは、経営の安定性維持の観点から注目されています。
M&Aによる事業承継も対象となります。第三者への事業譲渡を通じた事業存続も、選択肢として認められているのです。

ここでは、融資制度利用に向けた具体的な要件について説明します。
申込に際しては事業承継計画の策定が必須となり、後継者の存在も重要な判断材料です。金融機関による審査では、事業の継続性や成長性も含めた総合的な評価が行われるのです。
融資制度を利用するには、中期的な事業承継計画策定が必要不可欠です。経営者と後継者が共同で計画を作成することで、円滑な事業承継実現に向けて動いている方が対象です。
後継者による積極的な関与も重要です。事業承継計画には後継者育成プログラムや権限移譲スケジュールなど、具体的な取り組みを盛り込む必要があります。
対象となる事業形態は大きく分けて二つです。
一つ目は事業承継・集約を実施する、または実施される企業です。二つ目は事業承継を機に、第二創業(経営多角化・事業転換)や新規事業展開を図る企業です。
事業承継を単なる経営権移転に留めず、企業の持続的成長につなげる取り組みが評価されます。
事業承継計画には具体的な数値目標や実施スケジュールが必要です。計画の実現可能性は審査における重要な判断基準となります。
後継者要件として、経営者としての資質や能力が問われます。経営実務の経験や業界知識も重要な評価ポイントです。
企業の経営状況も詳細に確認されます。決算書類を通じた財務分析により、事業の継続性や成長性についても評価対象です。

事業承継・集約・活性化支援資金の申込には、各種書類提出が必要となります。事業承継計画を中心に、企業の現状と将来像を示す資料一式が求められるため、書類作成には相応の時間を要することを念頭に入れ、余裕を持って準備を進めましょう。
融資申込書では、資金使途や返済計画など基本的な借入条件を記載します。事業承継計画書には、承継スケジュールや経営方針など具体的な取り組みを明記します。
確定申告書は過去2~3年分が必要です。決算書類を通じて企業の経営状況や財務内容が確認されます。事業計画書では今後の経営戦略や数値計画を示します。M&Aや事業譲渡の場合は譲渡契約書も必要です。
商工会議所または商工会の推薦書が求められる場合があります。地域経済における企業の重要性や事業継続の必要性を示す資料です。
弁護士や公認会計士など専門家による意見書も重視されます。第三者的立場から事業承継計画の妥当性を評価する資料として必要とされるのです。
必要書類の詳細は日本政策金融公庫に確認しましょう。案件の特性に応じて追加書類が求められる可能性もあります。
各書類作成では具体性と一貫性が重要です。事業承継計画と事業計画の整合性確保も必須となります。書類不備は審査の遅延要因となるので注意しましょう。
記載漏れや押印忘れといった、形式面のミスにも注意が必要です。
提出時期にも留意しましょう。申請タイミングによっては決算期との関係で用意した書類が古い資料となる可能性もあり、タイミングを見計らった申込が求められます。

融資審査では事業承継計画の実現可能性が重点的に評価されます。
後継者の力量や事業の将来性など、多角的な観点からの審査が行われます。審査通過に向けたポイントを押さえておきましょう。
事業承継計画における具体性と実現可能性が問われます。 経営権移転から業務引継までの工程表や数値計画の妥当性が重要となります。
後継者の能力や適性も審査対象です。経営者としての資質に加え、 業界経験や実務能力も評価されます。また事業の収益性や成長性も重視されるため、 将来の事業展開や市場環境を踏まえた経営戦略が求められるでしょう。
資金繰り状況や返済能力も慎重に審査されます。特に過去3期分の決算状況が評価対象となり、 売上高の推移、利益率、自己資本比率、既存借入の負担率が重点的にチェックされます。 業績が低迷している場合は、改善策を明確に示すことが求められます。
事業承継計画は綿密に作り込む必要があります。承継スケジュールや経営方針など、具体的な取り組みを明確にしましょう。
後継者育成計画も重要です。権限移譲や実務経験の積み上げなど、段階的な育成プログラムが求められます。事業の将来性は積極的にアピールしましょう。成長分野への進出や新規事業展開など、企業価値向上に向けた取り組みを示します。
資金計画は現実的な案を設定しましょう。返済原資の確保や収支見通しの確実性を重視した計画策定が必要です。
提出書類は記載漏れや不整合がないか、入念なチェックを行ってから提出しましょう。
数値計画は妥当性の検証が重要です。売上予測や利益計画など、実現の可能性が高い数値設定が必要となります。事業計画の実現の可能性も確認しましょう。市場環境や競合状況を踏まえた現実的な計画策定が求められます。
事業承継・集約・活性化支援資金は、中小企業における円滑な事業承継実現を支援する融資制度です。申込に際しては事業承継計画の策定が必須となり、計画の具体性や実現可能性が重視されます。審査では後継者の資質や事業の将来性など、多角的な評価が行われます。本制度活用により、次世代への確実なバトンタッチを実現しましょう。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。