現在掲載中の企業73件

中小企業や個人事業主が事業を発展させるうえで欠かせない資金調達手段として、補助金と助成金が挙げられます。どちらも返済不要な公的資金ですが、実は運営主体や条件、用途などに明確な違いが存在します。
今回は補助金と助成金の基本的な違いや特徴、申込方法から注意点まで、資金調達を検討している経営者向けにわかりやすく解説しましょう。

両者は返済不要な公的支援金という点で同じですが、目的や仕組みに違いがあります。
補助金は事業そのものの発展や技術革新を促す資金であり、助成金は主に人材や労働環境の整備を支援する資金です。適切な制度を選ぶためにまずは基本的な違いを理解しましょう。
| 項目 | 補助金 | 助成金 |
|---|---|---|
| 目的 | 政策目標の達成、特定の産業・事業の育成・支援 | 雇用促進、労働環境改善、人材育成など |
| 管轄省庁 | 経済産業省、地方自治体など | 厚生労働省など |
| 財源 | 国や地方自治体の予算 | 雇用保険料など |
| 受給要件 | 審査あり、採択件数が限られる | 要件を満たせば受給可能 |
| 金額 | 比較的高額(数百万円~数千万円) | 比較的少額(数十万円~数百万円) |
| 主な対象 | 事業者(中小企業、大企業、個人事業主など) | 事業者(主に中小企業)、個人 |
| 例 | ものづくり補助金、事業再構築補助金 | キャリアアップ助成金、雇用調整助成金 |
補助金は、主に経済産業省や地方自治体が管轄しており、事業拡大や地域振興を目的とした企業活動を支援するために提供されます。経済発展や産業育成といった国や地域の政策目標達成のため、様々な制度が設けられています。
助成金は、主に厚生労働省が管轄しており、雇用促進や労働環境の改善を支援する制度です。従業員の賃金や職場環境整備、人材育成など、労働政策に関連した支援が中心となります。
補助金は新規事業の立ち上げや技術革新、設備投資を支援する目的があるのに対し、助成金は雇用の維持や従業員のスキルアップ、職場環境の改善など、人材や労働環境に関する支援が主な目的です。
補助金は申請後に審査・採択が行われ、選ばれた対象者のみに受給の権利が与えられる採択制です。限られた予算に対して多数の事業者が応募するため、競争率が高く、より具体的で実現性の高い事業計画の提示が求められるでしょう。
助成金は給付要件を満たせば給付を受けられるのが一般的で、条件を満たしていれば基本的に全ての申請者が受給できます。予め定められた条件をクリアしていることを証明できれば、比較的確実に受給できるという特徴があります。
補助金は公募期間が短いものの、給付金額が数百万~数千万円以上と比較的高額である場合が多いです。大規模な設備投資や技術開発など、企業の成長に直結するような大きなプロジェクトの資金として活用できます。
助成金は、公募期間に数ヶ月の余裕がある場合が多く、中には随時申請できる場合もありますが、金額は数十万円程度であるのが一般的です。短期間で結果が出るような、比較的小規模な取り組みに向いています。
補助金と助成金はどちらも返済不要の資金であり、要件を満たす個人事業主や法人の申請が必要で、原則として後払いである点は共通しています。事業遂行に必要な資金はまず自己負担し、後から支給される形となるため注意しましょう。

補助金は企業の成長や経済発展に寄与する投資を促進するためのものです。
特に中小企業や個人事業主にとって、大きな資金調達の手段となり得ます。ここでは補助金の申請から受給までの流れや活用のメリットをご紹介します。
補助金の申請は、申請準備、申請、採択結果の通知・交付申請、中間報告、交付決定・事業の実施、事業実績の報告・補助金の受給、事業状況の定期報告という流れです。
一連の流れは数ヶ月から場合によっては1年以上かかることもあり、計画的な準備が求められます。申請準備の段階では、自社の目的や必要金額を満たす補助金を選び、各補助金の概要や対象経費、補助金額などをしっかりと確認することが大切です。
事業計画書には自社の強みや事業の将来性、社会的意義などを具体的に盛り込むことが重要となります。申請書類は補助金を提供している機関や団体のWebサイトで入手可能で、採択されるためには事業計画書を具体的かつわかりやすく作成することが大切です。
審査では計画の実現可能性や独自性、市場性などが評価されるため、客観的なデータや根拠を示すことが採択率向上につながるでしょう。
補助金は新規事業の立ち上げや技術革新、設備投資を支援することを目的としており、企業の競争力強化や経済の発展への期待が込められているのです。事業の拡大や新分野への進出といった、通常では資金面で踏み出しにくい挑戦をサポートする役割を果たします。
また補助金は、採択されれば企業にとって新たな挑戦を支える重要な後押しとなります。採択率は補助金によって異なりますが、一般的に20〜30%程度で、事業計画の具体性や実現性が高く評価されるほど採択される可能性が高まるでしょう。
さらに補助金は、事業にかかった経費の一部を補助する形で支給される点が特徴で、地域活性化や環境対策、技術開発の促進など、政策目標に基づいた幅広い分野で活用されます。補助率は1/2〜2/3が一般的で、自己負担分があることを念頭に計画を立ててください。

ここでは補助金の具体例として、いくつか制度をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。この制度は、中小企業や小規模事業者が行う革新的なサービス開発、試作品開発、生産プロセスの改善などの設備投資を支援することを目的としています。
製造業に限らず、幅広い業種が対象です。補助上限額は、一般型の場合、従業員数に応じて750万円から1,250万円と設定されています。具体的には、従業員数5人以下で750万円、6~20人で1,000万円、21人以上で1,250万円となります。
この補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応し、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などを通じて規模の拡大を目指す企業や団体を支援する制度です。
補助金額は100万円から1億円と幅広く設定されており、具体的な金額や補助率は事業の内容や企業規模によって異なるので確認必須です。例えば、中小企業の場合、補助率は2/3で、補助金額は最大8,000万円となります。
また、従業員数101人以上の中小企業・中堅企業を対象とした「大規模賃金引上枠」では、補助金額が8,000万円超から1億円まで、補助率は中小企業で2/3(6,000万円超は1/2)、中堅企業で1/2(4,000万円超は1/3)と設定されています。
この補助金は、小規模事業者が経営計画を作成し、販路開拓や業務効率化などの取り組みを支援する制度です。地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上と持続的発展を目的とした補助金となります。
補助上限額は通常枠で50万円、特定の要件を満たす場合(例えば、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠)は最大200万円です。補助率は2/3で、赤字事業者については3/4に引き上げられます。さらに、インボイス特例の要件を満たす場合、上記補助上限額に50万円が上乗せされます。

助成金は主に人材確保や労働環境の改善に焦点を当てた制度です。
雇用促進や従業員教育など、人に関わる取り組みをサポートします。ここでは助成金の申し込みの流れ、活用する際のメリットについて解説します。
助成金の申請は、相談、助成金の診断、計画の立案、就業規則の確認・変更、計画書の届出・実施、助成金の支給申請、助成金の受給という流れで進みます。
助成金の種類によって細かい手続きは異なりますが、一般的には計画届の提出から実施、そして支給申請という段階を踏みます。
助成金はその種類によって受給までの手続きが異なるため、まずは専門家に相談することが望ましいでしょう。
企業の現状や目的に合った助成金を見つけるためにも、社会保険労務士や各地のハローワーク、労働局に相談することで適切な助成金制度を紹介してもらえます。
ただし、助成金の支給申請には期限が決められており、期限を過ぎると受給できなくなるため注意が必要です。多くの場合、要件達成後1〜2ヶ月以内に申請する必要があるため、カレンダーに期限を記入するなど、管理を徹底することが大切です。
助成金は、雇用の維持や従業員のスキルアップ、職場環境の改善など、人材や労働環境に関する支援が主な目的です。人材不足が深刻化する中、従業員の定着や能力向上を図るための取り組みをバックアップする制度として注目されています。
また助成金は、給付要件を満たせば給付を受けられるのが一般的で、条件を満たしていれば基本的に全ての申請者が受給できるため、計画的に活用しやすいです。事前に受給要件を確認し、計画的に取り組むことで、高い確率で受給することが可能となります。
さらに助成金は、公募期間に数ヶ月の余裕がある場合が多く、中には随時申請できる場合もあるため、企業の状況に合わせて柔軟に申請することが可能です。急な人員採用や教育訓練の実施など、企業側の都合に合わせて申請できる点も大きなメリットといえるでしょう。

ここでは助成金の具体例として、いくつか制度をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
この制度は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、無期雇用契約への移行を前提として、一定期間試行的に雇用する事業主に対して助成を行うものです。
対象となる求職者は、過去2年以内に2回以上の離職や転職を繰り返している方、1年以上の離職期間がある方、妊娠・出産・育児を理由に1年以上離職している方、55歳未満でニートやフリーターの方、生活保護受給者や母子家庭の母など特別な配慮を要する方などが挙げられます。
試行雇用期間は原則3か月で、事業主には対象者1人当たり月額最大4万円(母子家庭の母または父子家庭の父の場合は月額5万円)の助成金が最長3か月間支給されます。
この助成金は、過疎地域や離島、特定の産業が集積する地域など、雇用機会が不足している地域において、新たに事業所を設立し、地域の雇用促進と経済活性化を図る事業主を支援する制度です。
具体的な支給額は、創出する雇用人数や地域の指定要件などによって異なりますが、50万円から最大で800万円程度が支給される場合があります。助成金の活用により、地域の特性を生かした事業展開や、地域住民の雇用機会の拡大が期待されます。
この制度は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成を行うものです。
具体的には、非正規社員を正社員に転換した場合や、賃金規定を整備して基本給を増額した場合、職業訓練を実施してスキルアップを図った場合などが対象です。
支給額は、正社員転換の場合で30~80万円程度、賃金規定の整備や教育訓練の実施の場合で数万円から数十万円程度が支給されます。
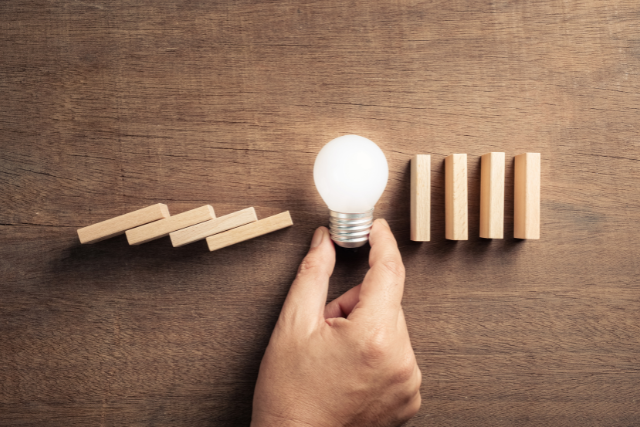
返済不要の公的資金として魅力的な補助金や助成金ですが、利用する際には注意すべき点も。資金面での準備や申請手続きの厳格さなど、押さえておくべき点を解説します。
補助金・助成金はいずれも事業の着手前には支給されず、事業実施後に支給される「精算払い(後払い)」であるため、事前に自己資金で費用を準備する必要があります。つまり、一旦は全額自社負担となる点を理解し、資金計画を立てることが重要です。
補助金では事業期間を定めるのが一般的で、この事業期間に支出した経費以外は経費として認められず、補助を受けられないことがあるため、支出時期に注意が必要です。
対象期間外の支出は、たとえ事業に関連する費用であっても認められないため、計画的な経費支出が求められます。
補助金活用の際は、申請した事業総額と同額の資金を用意する必要があり、例えば総額300万円の事業で1/3の補助がある場合は、まず自社のお金で300万円を支出する必要があります。資金繰りに余裕がない場合は、融資なども併用して準備することを検討しましょう。
補助金の申請書類を作成する際は、その補助金の目的をよく理解したうえで作成し、補助金の趣旨目的に沿っていることを申請書類に明示することが重要です。国や自治体の政策目標に合致した内容であることをアピールできれば、採択される可能性が高まります。
補助金はいつでも申請できるものではなく、公募期限が設けられているため、期限に余裕を持って準備を進めることが必要です。公募開始から締切までの期間が短い場合も多いため、日頃から情報収集を行い、募集開始と同時に準備に取りかかれる体制を整えておくことが望ましいでしょう。
助成金には支給申請ができる期間が決められており、1日でも過ぎると受付すらしてくれないため、期限の遵守が非常に重要です。要件達成後、いつまでに申請すべきかを確認し、社内でも共有しておくことで、申請漏れを防ぎましょう。
助成金を申請する際は、雇用保険適用事業所の事業主になっており、労働保険の滞納がない、審査に必要な書類を整備・保管している、管轄労働局が行う実地調査を受け入れるなどの要件を満たしている必要があります。
補助金申請で失敗しないためには、補助金の情報を幅広く収集する、制度の趣旨に沿った内容を記載する、申請書はわかりやすく作成する、添付資料の不足・漏れに注意するなどのポイントがあります。
専門家のアドバイスを受けながら進めることも効果的です。
補助金にはそれぞれ適用条件があり、自社の事業がその条件に合致していない場合は申請が通らないため、各補助金の募集要項をしっかりと読み込み、適用条件を十分に理解することが重要です。業種や企業規模、事業内容など、様々な条件があるため、自社が該当するかどうかを事前に確認しましょう。
補助金と助成金は、返済不要な公的資金という点で共通していますが、管轄機関や目的、申請・採択方法など多くの点で異なります。
補助金は主に事業拡大や技術革新を目的とし、競争型の採択制であるのに対し、助成金は雇用や労働環境改善が目的で、条件を満たせば基本的に受給できます。
どちらを活用する場合も、資金は後払いであることを念頭に置き、十分な自己資金の準備が必要です。申請書類の作成や期限の遵守は非常に重要であり、特に補助金の場合は採択されるための戦略的な事業計画の立案が求められます。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。