現在掲載中の企業73件

法人経営において避けたい状況である赤字決算。しかも赤字になれば全ての税金が免除されるわけではありません。今回は、赤字決算時に免除される税金と免除されない税金の違い、加えて赤字決算がもたらすメリットとデメリットについて解説しましょう。

法人が赤字決算を迎えた場合、税金はどうなるのでしょうか。
法人が赤字決算となった場合、所得に対して課税される税金は原則として免除されます。
法人税、地方法人税、法人事業税、特別法人事業税は課税対象となる所得がないため納付義務が発生しません。
法人税は法人の所得に対して課される国税であり、赤字の場合は所得がマイナスとなるため納付が不要になります。法人の利益に対する課税なので、利益がない場合は税金も発生しないという仕組みです。法人住民税のうち法人税割も、法人税額に基づいて計算されるため、赤字で法人税がゼロの場合は免除されます。
企業が赤字でも、支払いを免れない税金はいくつか存在します。代表的なのが「法人住民税の均等割」で、これは会社の規模(資本金や従業員数など)によって定額で課される税金です。利益が出ていようが出ていまいが、会社が存在するだけで毎年発生します。
他にも、会社名義で土地や建物を所有していれば「固定資産税」がかかり、営業車や社用車があれば「自動車税」や「軽自動車税」が発生します。また、契約書や領収書などに対して課される「印紙税」も、利益の有無に関係なく必要です。
さらに、売上はあるが利益が出ていないケースでは「消費税」の納税義務が生じることもあります。このように、企業はたとえ赤字でも、さまざまな形で税金を支払わなければなりません。
赤字でも税金が免除されない理由は、それらの税金が企業の「利益」ではなく、「存在」や「所有」「行為」に対して課されているためです。たとえば法人住民税の均等割は、企業が法人格を持って活動していること自体に対して課されるため、利益がなくても関係ありません。
同様に、固定資産税や自動車税も「資産や車両を持っていること」に基づく課税であり、会社が赤字であっても保有している限り税金が発生します。印紙税についても、一定金額以上の契約書を作成すれば自動的に課税対象です。
また、消費税は「売上に含まれる預かり金」としての性格が強く、仕入れなどで相殺できない場合は、たとえ赤字でも納税義務が残るかもしれません。つまり、これらの税金は「もうけが出ていないから払わなくていい」というものではなく、会社の活動そのものに対して課せられる性質のものなのです。
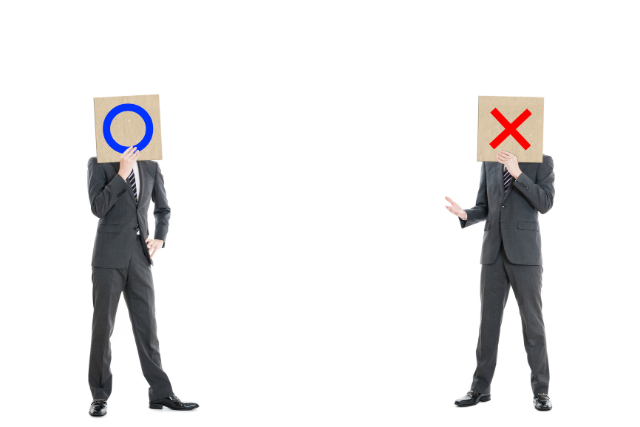
赤字決算は事業が順調でないことを示す指標ですが、税務面では一定のメリットもあります。また、対外的な信用面などではデメリットも。詳しく解説しましょう。
赤字決算のメリットとして、法人税や法人事業税、法人住民税の法人税割分が発生しなくなるため、キャッシュが少ない時期に税金負担が軽減されます。税金の支払いが減ることで手元資金に余裕が生まれ、資金繰りが楽になるかもしれません。
赤字となった金額は繰越欠損金として翌年以降に繰り越せ、最大10年間にわたって将来の黒字と相殺できるため、長期的な節税にもつながります。将来利益が出た際に過去の赤字と相殺できるため、税負担を軽減できる仕組みです。
また、中小企業に限り、赤字決算になった場合に前期に納税した法人税の一部が還付される制度があります。欠損金の繰戻し還付制度と呼ばれるもので、前年度に納めた法人税の一部が還付されるため、資金繰りの改善に役立つでしょう。
赤字決算のデメリットとして、金融機関からの融資を受けにくくなることが挙げられます。銀行は融資の判断材料として決算書を重視するため、赤字企業への融資には慎重になりがちです。
赤字が続くと取引先からの信用力が低下し、取引条件を見直されたり、最悪の場合は取引ができなくなることも。取引先は自社の信用リスクを避けるため、赤字企業との取引を制限することがあるのです。
赤字の状態が続けば企業の資金が減少し、倒産のリスクが高まるため、計画的でない赤字は経営上大きな問題となります。事業継続のためには黒字化に向けた対策が必要であり、赤字状態の放置は会社存続の危機につながりかねません。
赤字から脱却するためには、材料費や人件費といった経費の削減が効果的です。不要な支出を見直し、業務効率化によるコスト削減を図ることで利益率の改善が期待できます。
多角的事業展開を行っている場合は、赤字部門を切り離し、黒字部門に注力することも検討すべきです。経営資源を収益性の高い事業に集中させることで、会社全体の収益改善につながるかもしれません。

赤字決算でも税務上は特殊な処理が必要になる場合があります。創業時の特例や税務申告の際の注意点など、赤字決算時に理解しておくべき事項について解説しましょう。
会計上は赤字でも税法上は黒字となる場合があり、この場合は法人税などの税金が発生します。会計と税務では利益や所得の計算方法が異なるため、赤字だから税金がかからないと安心はできません。
会計上の利益は収益から費用を引いて求めますが、税法上の所得は益金から損金を引いて求めるため、両者は必ずしも一致しません。
税法特有の規定により、会計上の費用でも税務上は経費として認められないものがあるのです。
法人の交際費などは会計上は費用ですが、税法上は法人規模に応じた一定額までしか損金に計上できないため、会計上の赤字でも税務上は所得が生じる可能性があります。接待費や贈答品などの交際費は税務上の取扱いが厳しく、損金算入に制限があることを覚えておきましょう。
会計上の利益を基に税務申告を行った場合、修正申告や追徴課税の対象になることがあるため、税務上の所得を正確に把握するのが重要です。税務調査で指摘されないよう、適切な税務処理を心がけましょう。
赤字決算の場合でも、消費税や法人住民税の均等割など納付が必要な税金があるため、納税漏れを起こさないよう注意が必要です。赤字だからといって全ての税金の納付が免除されるわけではないという点を忘れてはなりません。
赤字決算の場合に免除される税金とそうでない税金を把握しなければ、納税漏れを起こすリスクや資金計画に影響する恐れがあります。納付期限や金額をきちんと把握し、納税資金を計画的に準備することが大切です。
創業したばかりの場合、赤字や黒字、売上高に関係なく消費税の納税義務は発生しないという特例があります。
設立1期目と2期目は原則として免税事業者となるため、消費税の納税義務から免除されるのです。
ただし、資本金額または出資金額が1億円を超える法人の場合は、創業時でも消費税の納税義務が発生する可能性があります。大規模な資本金で設立された法人には創業時の特例が適用されないケースがあるのです。
特定の条件を満たした場合は、免税事業者としてその年の消費税納税義務がなくなりますが、基本的には赤字でも消費税は免除されません。前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下なら免税事業者となる制度がありますが、赤字と免税事業者は直接の関係ありません。
法人が赤字決算となった場合でも、全ての税金が免除されるわけではないということがおわかりいただけたでしょうか。法人税や法人事業税など利益に課税される税金は免除されますが、消費税や法人住民税の均等割などは赤字でも納税義務があります。
赤字決算には税負担軽減や繰越欠損金の活用といったメリットがありますが、融資の難しさや取引先からの信用低下といったデメリットも存在します。赤字からの脱却には経費削減や事業再編、返済条件の見直しなどが有効な方法となるでしょう。
会計上の赤字と税務上の所得は一致しないケースもあるため、税務申告の際は専門家に相談するなど慎重に対応しなければなりません。正しい税務知識を身につけ、赤字決算時でも適切な経営判断ができるよう準備しておきましょう。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。