現在掲載中の企業73件

中小企業や個人事業主が事業資金を調達する手段として、制度融資が広く活用されています。公的な支援を受けられる制度融資は、一般的な銀行融資と比較して低金利で借入できる可能性があり、創業間もない企業や担保が不足している事業者にとって重要な選択肢です。今回は制度融資について詳しく解説しましょう。

制度融資は中小企業や個人事業主の経営を支援するために、地方公共団体が主体となって実施する公的融資制度です。民間金融機関からの融資と比べて、低金利かつ長期の返済期間が設定されており、中小企業の資金繰り改善や経営基盤強化に貢献しています。
制度融資は地方自治体・金融機関・信用保証協会の3者が連携して提供する公的融資制度です。
地方自治体が貸付原資の一部を負担し、信用保証協会が債務を保証することにより、金融機関が低利で融資を実行します。
融資実行の流れとしては、まず事業者が金融機関に融資の申し込みを行います。金融機関での審査後、信用保証協会による審査が行われ、両方の審査を通過して初めて融資が実行されますが、2段階の審査が必要なため、申込から着金までには約3か月ほどかかるかもしれません。
制度融資は公的資金を活用して1~3%程度の低金利を実現します。一方、銀行のプロパー融資では企業の信用度に応じて金利が決定され、制度融資より高めに設定されるのが一般的です。
審査面では、制度融資は信用保証協会の保証付きであるため審査に通過しやすい傾向があります。しかし金融機関と保証協会の2段階審査が必要なため、時間がかかるというデメリットも。
担保や保証人に関しては、制度融資では無担保・無保証人で借入できるメニューが多く用意されています。銀行融資では企業の信用力が不足している場合、担保や保証人が求められるケースが多いといえるでしょう。
都道府県や市区町村が制度融資の制度設計を行い、対象者や金利、融資限度額などのメニューを策定します。各自治体の産業振興策や地域経済活性化の方針に基づき、独自の融資制度が設けられていますので、自社の状況に合った制度融資を見つけるために、まずは各自治体の情報を確認してみましょう。
実際の融資手続きでは、指定金融機関が窓口となっており、地方銀行や信用金庫などが自治体からあっせん状を受けて融資申し込みを取り次ぎます。
信用保証協会は制度融資において極めて重要な役割を果たし、借り手が返済不能となった場合に金融機関への弁済を代行し、金融機関のリスクを軽減します。
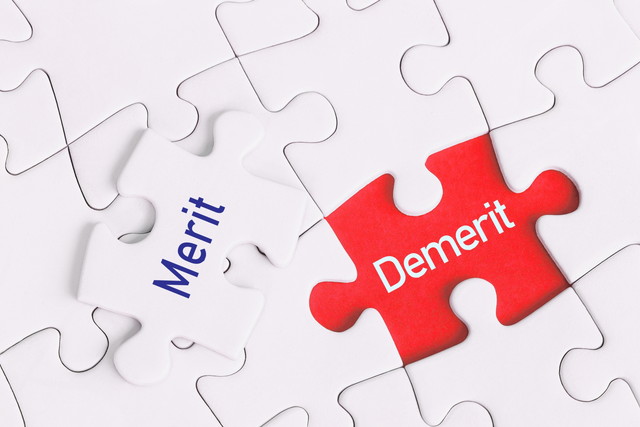
制度融資の活用を検討する際には、そのメリットとデメリットを理解することが重要です。低金利で借入できる利点がある一方で、手続きに時間がかかるなどの制約も。事業計画に合わせて総合的に判断しましょう。
制度融資の最大のメリットは 低金利で長期借入が可能である点です。創業間もない企業や業績が不安定な時期でも、資金調達コストを抑えることができます。
信用保証協会の保証付きであるため、 実績や担保が少ない事業者でも審査を通過しやすくなっています。創業期や小規模事業者にとって、他の融資制度では難しい資金調達の道が開かれるかもしれません。
融資メニューによっては 据置期間を設定できるほか、長期返済プランも用意されています。資金繰りの負担を軽減しつつ事業展開できる点は、特に成長過程にある企業にとって大きな利点となるでしょう。
制度融資のデメリットとして、申し込みから融資実行までに時間がかかる点が挙げられます。通常、平均3か月程度を要するため、急な資金需要には対応しづらいといえるでしょう。
また、自治体ごとに制度内容や金利・利用条件が異なるため、複数の制度を利用する場合は都度確認が必要です。事業展開が複数の地域にわたる場合、各地域の制度を個別に調査する手間が生じます。
さらに、融資上限額が設定されており、大口資金調達には向かないかもしれません。事業規模が大きくなるにつれて、制度融資だけでは資金需要を満たせなくなる可能性も考慮に入れておく必要があるでしょう。
制度融資では、最終的に金融機関の審査合格後に保証協会の承諾が必要です。金融機関だけの審査を通過しても、保証協会で承認されなければ融資決定とはなりません。
また、自治体によって保証料や利子補給の補助の有無が異なります。
場合によっては保証料が発生するケースもあるため、総コストを事前に確認しておきましょう。
利用時はあらかじめ窓口となる金融機関を選定し、担当者の了解を得てから申請を行う必要があります。

制度融資を利用するためには、定められた審査プロセスを経て必要書類を揃える必要があります。各自治体や金融機関によって利用条件が異なるため、事前に詳細を確認しておくことが重要です。
制度融資は金融機関と信用保証協会の2段階審査を経て融資可否が決定します。まずここを突破しなければなりません。
金融機関では事業の安定性や収益性、返済能力などを評価し、保証協会では保証リスクの観点から審査が行われます。
審査過程では事業計画や財務状況、返済能力が詳細に評価されます。自治体の経営指導などが求められる場合もあり、事業の将来性も判断材料の1つとなるでしょう。
急ぎの資金調達には向かない特徴があり、申し込みから着金まで平均約3ヶ月かかります。そのため、資金需要を事前に予測し、計画的に申請することが重要です。
融資あっせん依頼書、融資依頼書、信用保証委託申込書などの申込書類一式を取扱金融機関または保証協会で入手します。
必要事項を漏れなく正確に記入しましょう。
直近2期分の決算書または試算表、市税納税証明書、法人登記簿謄本の写しなどが基本的な必要書類です。財務状況や事業実績を示す資料として、審査の重要な判断材料となります。さらに、許認可業種は許可証の写し、建設業では受注工事明細書など業種別資料も求められますので、準備しておきましょう。
資本金や従業員数など一定規模以下の中小企業・小規模事業者が対象となる要件が自治体ごとに設定されています。一般的には中小企業基本法に定める中小企業者が対象です。
保証対象外業種や許認可業種は事前に条件を確認し、必要な許認可を取得しておくとよいでしょう。業種によっては制度融資の対象外となるかもしれません。
利用条件は地方自治体や金融機関によって異なるため、事前に取扱金融機関や保証協会へ問い合わせて確認しましょう。

制度融資が利用できない場合や、審査期間の長さから緊急の資金需要に対応できない場合もあります。そうした状況でも事業資金を確保するための、他の調達手段について解説していきましょう。
日本政策金融公庫の新規開業資金は無担保・無保証人で最大7,200万円の融資が可能で、特別利率制度もあります。政府系金融機関として創業支援に力を入れており、民間金融機関より有利な条件で融資を受けられる場合が多いです。
民間金融機関のプロパー融資は企業の信用力や実績に応じて金利・融資額が決まり、審査スピードが比較的早いという特徴があります。
両融資とも条件や金利、審査時間が異なるため、事業規模や資金用途に応じて選択しましょう。
ファクタリングは売掛債権をファクタリング会社に売却し、手数料を差し引いた額を即日受け取る資金調達手法です。
銀行融資と異なり借入ではないため、負債として計上されず財務状況への影響が少ないメリットがあります。
2社間ファクタリングは手数料が高いものの、取引先に利用を知られずに資金化できるため、売掛先との関係性を維持したまま、迅速な資金調達が可能です。
3社間ファクタリングは手数料が低い一方で売掛先への通知義務があり、信用不安を招くリスクが否めません。
補助金・助成金は返済不要な公的支援制度で、国や自治体が公募する各種プログラムから申請できます。特定の政策目的に沿った事業計画が採択されれば、自己資金の何倍もの資金を獲得できるかもしれません。
補助金は成果報告や書類提出が求められ、申請競争が激しいため早めの情報収集が必要です。採択率が低い場合もあるため、申請書の作成には慎重な準備が望ましいでしょう。
助成金は条件を満たせば随時支給されるものもあり、人材確保や設備投資など特定用途で活用しやすいです。
制度融資は低金利・長期返済という好条件で中小企業の資金調達を支援する公的融資制度です。地方自治体・金融機関・信用保証協会の3者連携によって実現し、特に創業間もない企業や担保が少ない事業者に有効といえるでしょう。
審査に時間がかかる点や融資上限額があるという制約はあるものの、計画的に活用することで資金繰りの安定化が図れます。日本政策金融公庫融資やファクタリングなど別の調達方法も検討し、事業状況に最適な資金調達戦略を構築しましょう。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。