現在掲載中の企業73件
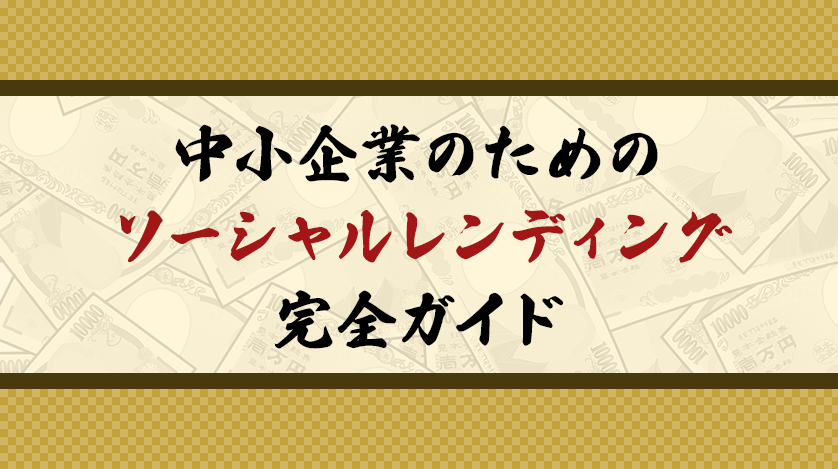
中小企業の間で、従来の銀行融資とは異なる資金調達手段である「ソーシャルレンディング」が注目を集めています。インターネットを活用した新しい融資の仕組みは、実績の少ない企業や緊急の資金需要に対応できる可能性を秘めています。
そこで今回は、事業資金の調達における選択肢を広げるため、ソーシャルレンディングの基本的な仕組みやメリット・デメリット、利用時の注意点について詳しく解説しましょう。

ソーシャルレンディングは、インターネット上で投資家と資金需要のある事業者を結びつける融資仲介サービスです。従来の金融機関を通さずに資金調達ができる新しい仕組みとして、中小企業の資金繰りに新たな可能性をもたらしています。
ソーシャルレンディングは、クラウドファンディングの一種として位置づけられています。
運営会社が投資家から小口資金を集め、中小企業に融資し、元本と利息を返済する仕組みが基本的な構造です。
銀行融資と異なり、プロジェクト単位での資金調達が可能で、新興企業でも利用しやすい環境が整っています。投資家は1万円程度の少額からでも参加ができ、運営会社が集めた資金を借り手企業に融資する形です。
運営会社は第二種金融商品取引業の登録を受けており、金融庁の監督下で事業を行っています。貸金業法とは異なる規制の下で運営されているため、従来の金融機関とは異なる審査基準や融資条件を設定できる特徴があります。
審査スピードが銀行より早く、数日で資金調達が可能な点が大きな違いです。銀行融資では通常1か月以上かかる審査期間が、ソーシャルレンディングでは大幅に短縮されています。
金利は銀行より高い傾向があるものの、実績の少ない企業でもプロジェクトの内容次第で融資を受けられる可能性があります。
担保や過去の業績よりも、事業計画の妥当性や将来性を重視するため、スタートアップ企業にとって利用しやすい融資形態です。
銀行融資では個人保証や担保が求められることが多いですが、ソーシャルレンディングでは事業の内容や収益性に基づいた審査が行われます。経営者個人の信用力よりも、事業計画そのものの実現可能性が判断材料となるのが特徴です。
投資家は運営会社を通じて少額から出資し、貸付債権を取得する形で参加します。運営会社は複数の投資家から資金を集め、借り手企業に対してまとまった金額の融資を実行します。
運営会社は元本と利息を回収後、手数料を差し引いて投資家に分配することが役割です。貸し倒れが発生した場合は元本割れリスクがあり、投資家が損失を負担することになります。
借り手企業は返済遅延や倒産がなければ、計画通りに資金を活用できます。返済方法は元本一括返済や分割返済など、プロジェクトの性質に応じて設定され、運用期間は数か月から2年程度が一般的で、期間中は投資家による途中解約はできません。
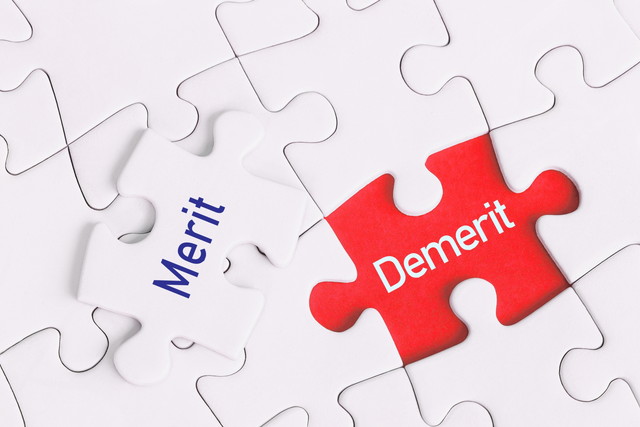
ソーシャルレンディングは従来の融資方法とは異なる特徴を持っており、中小企業にとってメリットとデメリットの両面があります。
小額から資金調達が可能で、個人投資家の幅広い参加を促せる点が大きなメリットです。1万円程度の少額投資から始められるため、多くの投資家が参加しやすく、結果として事業者にとっても資金を集めやすい環境が整っています。
プロジェクトのプレゼン力次第で、実績の乏しい企業でも調達できる可能性があります。事業計画の説得力や将来性が評価されれば、過去の業績が不十分でも融資を受けることができるでしょう。
運営会社や投資家に対して事業内容を効果的にアピールできれば、従来の金融機関では評価されにくい新規事業でも、資金調達の機会を得ることができるでしょう。
元本割れリスクがあり、貸し倒れ発生時は投資家に損失が発生する構造です。投資家にとってのリスクが高い分、借り手企業も高い金利を負担する必要があり、資金調達コストが増大する要因となります。
基本的に途中解約が不可能で、運用期間中は資金が拘束される制約があります。投資家は運用期間満了まで資金を引き出せないため、流動性の観点で制限が生じてしまうでしょう。
手数料や金利が銀行より高めに設定されており、返済負担が増大する可能性があります。運営会社の手数料や投資家への利回りを考慮すると、総合的な資金調達コストは銀行融資を上回ることが一般的です。短期的な資金需要には対応できるものの、長期的な事業運営においては負担が重くなる場合があるでしょう。
銀行融資の審査に通らないスタートアップや、短期資金が必要な企業に適しています。創業間もない企業や業歴の浅い事業者でも、事業計画の内容次第で資金調達が可能です。
例えば、事業拡大のタイミングで資金が必要になった場合、市場機会を逃さないために短期間での調達が求められる場面では、ソーシャルレンディングが有力な選択肢です。従来の金融機関では対応困難なケースでも、迅速な資金調達を実現できる可能性があるでしょう。

ソーシャルレンディングを利用する際は、運営会社の選定から投資先の分散まで、複数の要素を慎重に検討する必要があります。適切な判断基準を持って取り組むことができれば、リスクを最小限に抑えながら資金調達を実現できるでしょう。
金融庁登録の有無を必ずチェックすることが重要です。
第二種金融商品取引業の登録を受けている運営会社のみが、ソーシャルレンディング事業を適法に運営できます。
過去の実績や情報公開の積極性を評価し、虚偽記載のない業者を選ぶ必要があります。運営会社のウェブサイトや報告書で、融資実績や延滞率などの情報が適切に開示されているかを確認しましょう。
提示されたファンドの内容が、自社の資金ニーズと合致しているかを確認することも大切です。たとえば、元本一括返済か分割返済かといった返済方式や、運用期間、募集金額、手数料などの条件が、資金繰りに無理のない内容かを事前にチェックしましょう。
返済条件が自社の経営実態に合わなければ、後々の資金繰り悪化につながる可能性があります。
資金を調達するには、投資家に対して自社の事業の信頼性を伝える必要があります。
そのため、事業内容、資金の使い道、財務状況などを具体的に記載し、信頼される情報発信を行うことが欠かせません。情報開示が不十分だと審査に通りにくくなったり、投資家が集まらずに資金調達が不成立となるリスクもあるため注意が必要です。

ソーシャルレンディングは柔軟な資金調達手段である一方、仕組みや契約内容を誤解したまま利用するとトラブルにつながるおそれがあります。利用前には、潜在的なリスクを十分に理解し、必要な備えを講じることが重要です。
返済原資を明確にしないまま借入れを行うと、将来的な資金繰りに支障をきたす可能性があります。ソーシャルレンディングは運用期間中の繰上返済が難しい場合もあり、急な資金需要には対応できないケースがあります。
運用期間は、3か月から2年程度と幅があるため、その間のキャッシュフローを見越した資金計画が必要です。事業資金のうち、短期で必要になる分と分けて考え、無理なく返済できる範囲で借入れ額を設定しましょう。
また、万が一のケースも想定したリスク管理も重要です。売上の急減や取引先の倒産など、返済が難しくなる事態を事前に想定し、事業に深刻な影響を与えない水準で調達額を抑える判断も必要です。
利回り(出資者側の期待利益)が高い案件は、資金調達側にとってもリスクの高い条件が設定されていることがあります。たとえば、担保や保証が求められる、あるいは返済条件が厳しいなどのケースです。
「年率10%超」などのファンドは、借り手企業にとっても返済負担が重くなるため、資金繰りの悪化を招くリスクがあります。
表面上の利回りではなく、契約全体を見て、自社に適した条件かどうかを見極めましょう。
調達後の返済スケジュールや担保条件、融資期間とのバランスも検討ポイントです。条件に不明点があれば、早めに運営会社に確認し、納得できない点がある場合は利用を控える判断も視野に入れるべきです。
ソーシャルレンディングでは、資金のやり取りや管理を行う運営会社が間に入ります。そのため、運営会社の財務状態や経営状況が不安定な場合、自社の借入にも影響が出る可能性があります。
過去には、運営会社の破綻によって融資実行が遅れたり、資金が宙に浮いたままになるといったトラブルも発生しているため注意が必要です。契約前には運営会社の金融庁登録状況や業界内での評判、過去の行政処分歴なども確認しておきましょう。
取引開始後も、運営会社の方針変更や経営悪化などに備えて、定期的に情報収集を続ける姿勢が大切です。不安な点が出てきた場合は、専門家に相談することで、事前にリスク回避ができる可能性があります。
ソーシャルレンディングは中小企業にとって新たな資金調達手段として有効な選択肢です。銀行融資と比べて審査が迅速で、実績の少ない企業でも利用できる可能性があります。
一方で高い金利や元本割れリスクなど、デメリットも存在するため慎重な検討が必要です。運営会社の信頼性確認や分散投資の徹底など、適切なリスク管理を行いながら活用することが重要です。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。