現在掲載中の企業73件

中小企業や個人事業主にとって、売掛金は事業存続の生命線です。しかし、未回収の売掛金が時効を迎えると請求権が消滅し、回収が法的に不可能になります。売掛金の時効期間や更新方法を正しく理解し、適切な対処をすることで債権を守りましょう。

2020年に民法が改正され、売掛金の時効期間が変更されました。ここでは、旧民法と新民法の違いや時効の起算点など基本知識について解説します。
旧民法では売掛金の時効は、債権の種類によって区別が存在しました。
商取引から生じる商事債権は2年、一般的な貸金などの民事債権は5年と定められていました。
2020年4月1日以降の新民法では、商事債権と民事債権の区別が廃止されました。
全ての債権の消滅時効が原則5年(権利行使可能と知った時から)または10年(権利行使可能な時から)に統一されています。
新民法施行前に発生した債権には旧民法が適用され、施行後に発生した債権には新民法が適用されます。
商事債権と民事債権の区別がなくなったことで、取引形態による時効期間の違いを気にする必要がなくなりました。全ての債権の消滅時効期間が5年に統一されたことで、管理が容易になったと言えるでしょう。
売掛金の時効の起算点は、原則として商品やサービスの提供が完了した時点から開始します。請求書の発行日や支払期日ではなく、債権者が権利行使可能となった時点が起算点になるので覚えておくと良いでしょう。
具体的には、商品の納品が完了した日や、サービス提供が終了した日から時効が進行します。継続的なサービス契約の場合は、各サービス提供時期ごとに個別の債権として起算点が設定されることもあるため注意が必要です。
時効は起算点から5年が経過した時点で、債務者が「時効の援用」をすると債務から解放されることになり、債権者は法的な請求権を失うことになります。
継続的な取引の場合、最後の取引日が時効の起算点となる場合があります。毎月の継続取引では、最終取引日から時効が進行すると解釈されるケースもあるため、取引記録を正確に保管しておく必要があります。
分割払いの契約では、各支払期日ごとに時効が進行します。例えば10回の分割払いなら、それぞれの支払期日から個別に5年の時効期間が計算されるため、最終的な時効完成時期は最後の支払期日から5年後となります。
債権者と債務者との間で時効について協議を行う旨の合意をした場合、最長1年間まで時効の完成を猶予することが可能です。1年間の猶予期間内に再度合意がなされれば、さらに1年間猶予されます。
協議による猶予期間を繰り返すと、本来時効が完成すべき時から最長5年間、時効を猶予させることができます。協議合意は書面で行い、日付と両者の署名を残しておくことで後々のトラブルを防止できるでしょう。

時効が迫っている売掛金債権を守るためには、積極的に時効を更新する行動が必要です。法的な手続きから債務者との交渉まで、状況に応じた方法を選択することが大切です。
訴訟の提起や支払督促の申立てにより時効の完成は猶予され、請求が認められると時効期間を更新させることができます。裁判所を通じた請求は、後述する時効の完成猶予事由の1つで、債権者の権利行使の意思を明確に示すものとして扱われるためです。
裁判上の請求は、認められることで時効を更新できますが、費用や時間もかかるため、債権額や債務者の支払能力などを考慮して判断することが望ましいでしょう。少額の債権に対して、高額な裁判費用をかけることは経済的合理性に欠けます。
債務者が債務の存在を認めることで、時効を更新させることができ、これを「債務承認」といいます。
債務承認は比較的容易に行える方法であり、債務者との関係を維持しながら債権保全できるのが利点です。
債務承認には、一部弁済や利息の支払い、債務承認書の作成などがあります。一部でも支払いがあれば、債務者が債務の存在を認めたと解釈され、その時点で時効が更新されます。
債務承認は書面で行うことが望ましく、日付と債務者の署名があるとなお良いでしょう。口頭による承認でも法的には効力がありますが、後日の「言った・言ってない」紛争を避けるためにも、書面化しておくことが強く推奨されます。
債務者の財産に対する差押えや、仮差押えをすることで時効の完成猶予が可能です。債務者の所有する不動産や預金口座などの財産に対して法的な制限をかけることで、最終的に時効を更新させることが可能となります。
ただし、差押えや仮差押えは裁判所を通じて行う必要があり、専門家のサポートが推奨されます。手続きが複雑で専門知識が必要なため、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談することが現実的です。
差押えや仮差押えの手続きは、債権者が積極的に債権回収の意思を示すものとして扱われます。単なる請求や催促と異なり、法的な強制力を伴う手段であるため、債務者に対して強いプレッシャーとなるでしょう。
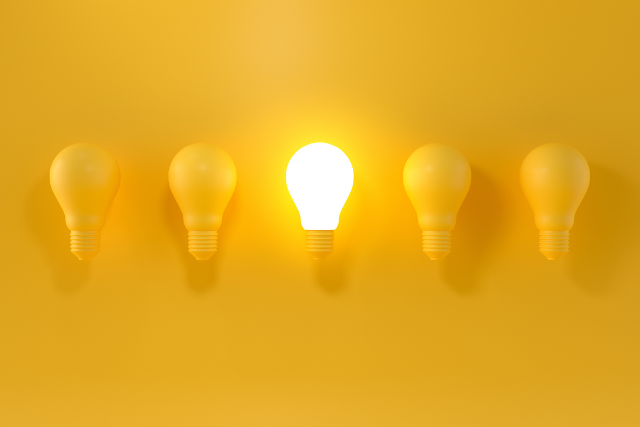
時効の完成猶予とは、一定の事由によって時効の進行が一時的に止まる状態を指します。債務者との協議や不可抗力の事態など、様々な状況下で時効の完成は猶予されます。
天災、その他避けることのできない事変により権利の行使が妨げられた場合、障害が消滅してから3ヶ月以内の期間は時効の完成が猶予されます。
不可抗力によって、債権者が権利行使できない状況を考慮した規定です。具体的には、地震や台風などの自然災害、戦争、内乱などが該当します。
例えば、大規模災害の復旧に時間がかかる場合でも、状況が正常化してから3ヶ月間は時効が猶予されるため、権利行使の機会が保障されています。ただし、何が「避けることのできない事変」に該当するかは解釈の余地があるため、明確な判断が難しいケースもあります。
法定代理人がいない未成年者や成年被後見人の債権については、時効の完成が猶予されます。これは、権利行使が困難な立場にある人々を保護するための規定です。
法定代理人が選任されるまでの間は、時効の進行が一時的に猶予されます。また、代理人が就任した後も、状況把握や適切な対応を行うために、就任から6ヶ月が経過するまでは時効の完成が猶予されます。
事業者間の取引では適用場面は限られますが、相続などで債権者が未成年者となる場合には重要な意味を持つでしょう。同様に、債務者が未成年者や成年被後見人である場合にも適用されるため、双方を保護する仕組みとなっています。
売掛金の時効は新民法において5年に統一されました。時効の更新や完成猶予を理解し、適切なタイミングで対応することが債権を保全するためには重要です。裁判上の請求や債務承認、協議合意や天災による停止制度を状況に応じて活用しましょう。
時効管理においては、起算点を正確に把握し記録を残すことが最も重要です。債権管理表を作成して定期的に確認する習慣をつけ、時効が迫っている債権には優先的に対応することで、不測の損失を防ぐことができます。また、債務者との良好な関係を維持しながら時効対策を行うことで、円滑な債権回収が可能になるでしょう。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。