現在掲載中の企業73件

サプライチェーンファイナンスは、製造から販売までの流れにおける資金調達を効率化する金融サービスとして注目を集めています。企業が部品や原材料を調達する過程で発生する資金需要に対応し、サプライチェーン全体の資金繰りを改善する仕組みです。中小企業や個人事業主にとって新たな資金調達手段として認識されつつあります。

サプライチェーンファイナンスは、企業間取引における資金繰りを円滑にする金融手法として広がりを見せています。従来の融資とは異なり、取引そのものに金融機関が関わることで、より柔軟な資金調達が可能になりました。売り手と買い手双方にメリットをもたらす点が大きな特徴です。
サプライチェーンファイナンスは、企業の構築する部品や原材料の供給網に金融機関が関与し、売掛債権の購入などを実施する金融サービスです。
製品の製造現場から小売店頭に並ぶまでの過程で発生する資金需要に対応し、各企業の資金繰りを支援します。
金融機関が商品や製品の供給元(サプライヤー)の信用力を評価し、取引先企業(バイヤー)に代わって代金を立て替えて払う仕組みが基本です。サプライヤーは納品後すぐに資金化できるメリットがあり、バイヤーは支払いタイミングを調整できるため、双方にとって魅力的な選択肢になり得ます。
サプライヤーは金融機関に承認された請求書を渡すことで、すぐに債権額に応じた金額の支払いを金融機関から受け取ることが可能です。通常なら支払期日まで待たなければならない資金を前倒しで獲得できるため、日々の運転資金に余裕が生まれます。
バイヤーは指定された期日に金融機関へ商品の代金を支払うため、実質的に支払い期間を延長できます。資金の流出タイミングをコントロールしやすく、資金繰り計画が立てやすくなるでしょう。双方の資金繰りニーズを同時に満たす点がサプライチェーンファイナンスの大きな魅力です。
サプライチェーンファイナンスは、複雑なサプライチェーンを持つ企業、多くのサプライヤーと取引する企業、大手バイヤーとの取引が多い企業、成長中の企業、在庫管理に課題がある企業、ITシステムが整っている企業、サプライチェーンマネジメントに関心が高い企業に向いています。
これらの企業は、サプライチェーンファイナンスによって資金繰りを改善し、サプライチェーン全体を最適化することができるでしょう。

サプライチェーンファイナンスとファクタリングは一見似ている金融サービスですが、重要な点で異なります。以下の表では両者の主な違いを整理しています。資金調達を検討する際は、事業規模や取引状況に応じて適切な方法を選択することが大切です。
| サプライチェーンファイナンス | ファクタリング | |
|---|---|---|
| 目的 | サプライチェーン全体の効率化 サプライヤーの資金繰り改善 | 売掛金の早期資金化 |
| 主体 | 主にバイヤー(買い手) | サプライヤー(売り手) |
| 契約形態 | 主に三者間契約(バイヤー、サプライヤー、金融機関) | 主に三者間契約(サプライヤー、バイヤー、ファクタリング会社) |
| 資金調達方法 | 主にバイヤーの信用力を活用した融資 | 売掛債権の譲渡 |
| 手数料 | バイヤー負担 | 主にサプライヤー負担 |
| メリット | サプライヤーの資金繰り改善 バイヤーの仕入コスト削減 サプライチェーン全体の安定化 | 即時の資金調達 財務状況の改善 |
| デメリット | 契約手続きが煩雑 バイヤーの信用力に依存 | 手数料が高い 売掛債権の回収リスク |
上記の表から分かるように、両者は主体となる企業や契約形態、手数料体系などが大きく異なります。自社の状況に合った資金調達手段を選択するためには、それぞれの特徴を十分に理解しておくことが重要です。
サプライチェーンファイナンスは主に発注者(バイヤー)が主体となり、3社間(バイヤー、サプライヤー、金融機関)で契約を結びます。大企業が主導して自社のサプライチェーン全体の資金繰りを最適化することを目的としているため、バイヤー主導型の仕組みになっています。
ファクタリングは受注者(サプライヤー)が主体となり、主に3社間で契約を結ぶことが可能です。売掛金の早期現金化を目的とするサプライヤーが主導して利用するケースが多いでしょう。
サプライチェーンファイナンスは大手銀行が取り扱うことが多く、ファクタリングは専門のファクタリング会社が主に取り扱います。金融機関の種類によって審査基準や手数料体系が異なるため、利用を検討する際は複数の金融機関を比較検討することが賢明です。
サプライチェーンファイナンスの手数料は比較的低く、1~9%程度となることが多いです。バイヤーの信用力を基に融資判断がなされるため、信用リスクが低く抑えられることが理由として挙げられます。
ファクタリングの手数料は契約形態によって異なり、2社間の場合は8~20%、3社間の場合は1~9%程度となります。特に2社間契約の場合は、サプライヤーの信用力のみで判断されるため、リスクに応じて手数料が高くなりがちです。
サプライチェーンファイナンスは発注者の信用力を基に行われるため、信用リスクが低く、手数料も比較的安価になります。大企業を中心とするサプライチェーン全体で考えると、全体最適の観点から資金調達コストの低減が図られている点が特徴的です。
サプライチェーンファイナンスは利用のハードルが高く、でんさいネット(株式会社全銀電子債権ネットワークが運営する、電子記録債権による決済サービス)への加入が必要条件となります。電子的な債権管理が前提となるため、IT環境の整備が必要になる点も考慮すべきでしょう。
ファクタリングは比較的利用しやすく、審査も簡単ですが、手数料が高くなる傾向がありますが、急な資金需要に対応するための手段として、中小企業や個人事業主に広く利用されています。
サプライチェーンファイナンスは大企業をコアとするサプライチェーン全体の資金繰り効率化に適しており、ファクタリングは個別の売掛債権の現金化に適しています。
自社の状況に応じて、適切な資金調達手段を選択するとよいでしょう。
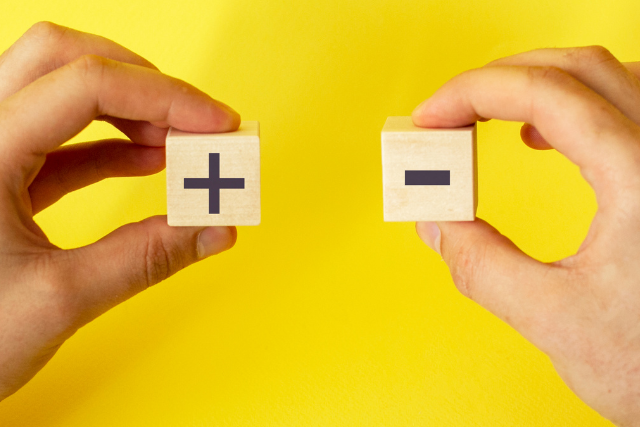
ここではサプライチェーンファイナンスにおける 発注者(バイヤー)・ 受注者(サプライヤー)メリットと、双方における共通のデメリットについて詳しく解説します。
買掛金を支払う時期を先延ばしできるため、資金繰りが厳しい場合でもさらなる仕入れが可能です。運転資金に余裕が生まれることで、事業拡大の機会を逃さず、より積極的な経営判断ができるようになるでしょう。
まとまった資金を確保できるタイミングに合わせて金融機関への支払いの時期を調整でき、資金繰りを改善できます。
季節性のある事業や、大型案件の入金タイミングに合わせた支払い計画が立てやすくなるでしょう。
売掛金を支払期日よりも早く回収できるため、資金繰りの改善につながります。資金回転率が向上することで、新たな事業機会への投資や事業拡大がスムーズになるでしょう。
売掛金があるにもかかわらず倒産する「黒字倒産」のリスクを回避できます。中小企業にとって、売掛金の回収遅延は経営危機に直結することがありますが、サプライチェーンファイナンスを活用することでキャッシュフローが安定します。
発注者(バイヤー)の貸し倒れによる未払いのリスクがなく、安定的な資金調達が可能です。取引先の信用リスクを金融機関が負担してくれるため、安心して商取引に集中できるようになります。
利用のためのハードルが高く、取り扱っている金融機関は大手の銀行などに限られます。中小企業単独での利用は難しいケースが多く、大企業のサプライチェーンに組み込まれている企業が対象となることがほとんどです。
双方の企業がでんさいネットへ加入することが必要要件となり、審査を通るためにはある程度の信用が必要です。電子的な債権管理システムの導入コストや運用負担も考慮しなければなりません。
サプライチェーンファイナンスは企業間取引の資金繰りを改善する効果的な金融手法です。サプライヤーの早期資金化とバイヤーの支払い期間延長を同時に実現し、サプライチェーン全体の最適化に貢献します。大企業を中心としたサプライチェーン全体で活用されることが多く、中小企業単独での利用はハードルが高いものの、大企業との取引がある中小企業にとっては魅力的な資金調達手段となり得ます。
自社の状況に合わせて、サプライチェーンファイナンスとファクタリングを使い分けることで、より効率的な資金繰り管理が可能になるでしょう。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。