現在掲載中の企業73件

法人税の納付期限が迫っているにもかかわらず、資金不足で支払いができない状況は多くの経営者が直面する問題です。今回は法人税の滞納による影響を解説しましょう。
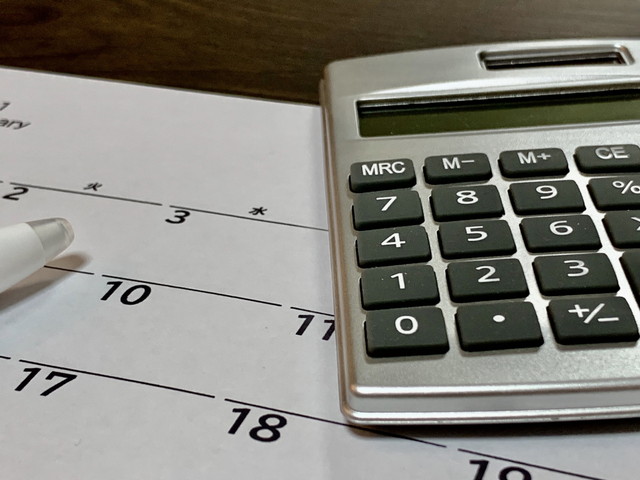
法人税の納付期限を過ぎるとどうなるのでしょうか。わかりやすく解説しましょう。
法人税を期限までに納付できなければ、未納額に対して一定の割合の延滞税が発生します。支払いが遅れるほど負担は増加。
納付期限の翌日から2か月以内は年率2.4%、2か月経過後は年率8.7%(令和6年の場合)が適用されます。
延滞期間が長くなるほど延滞税は高額になり、納税額が増えるため早急に支払わなければなりません。延滞税は本来の納税額に上乗せされる形で課されるため、資金繰りがさらに厳しくなる原因になります。わずかな遅れでも延滞税は発生するため、期限内の納付が望ましいでしょう。
法人税の支払いが滞ると、税務署から督促状が送付され、電話、文書、訪問による催告が行われます。納税を促す連絡は徐々に頻度が増し、督促状は納付期限から1か月程度(50日以内)の滞納で送付され、差し押さえに向けた動きが開始します。
督促状は納税者への最終通告的な性質を持つ重要な書類です。督促状が届いても納付されない場合、税務署は催告と並行して法人の財産調査を行います。滞納処分の準備が進められるため、督促状を受け取った段階で早急に対応しなければなりません。
法人税を滞納したことが取引先や顧客に知られると、会社の社会的信用が大きく低下します。経営状態に問題があると判断され、新規取引の停止や既存契約の見直しにつながるかもしれません。
預金や売掛金が差し押さえられた場合、その事実が取引先に伝わり、取引関係の見直しや解消につながることも。銀行取引にも影響し、融資が受けられなくなる可能性もあります。

法人税の滞納から差し押さえに至るまでには一定の流れがあります。詳しく解説しましょう。
法人税を滞納すると、納付期限から1か月程度(50日以内)で督促状が送付されます。督促状は差し押さえへの最初の告知であり、重要な法的文書です。
督促状が発送された日から起算して10日後が新たな納付期限となり、この期限までに完納しないと差し押さえの対象となります。
短い期間で対応が求められるため、督促状が届いたらすぐに行動しなければなりません。法律上、督促状発送から10日が経過しても税金が完納されない場合には差し押さえされることが定められています。財産差し押さえは法的手続きであり、税務署の裁量で回避できるものではない点に注意しましょう。
督促状が届いても納付されない場合、税務署から電話や書面などで納付を催告されます。複数の手段で連絡が入ることで、納税を促す圧力が強まるといってよいでしょう。税務署の職員が訪問して催告することもあり、これらは差し押さえに向けた法的手続きの一環です。
対応が不誠実だと判断されると、差し押さえの手続きが加速するかもしれません。税務署は催告と並行して法人の財産調査を行い、差し押さえの準備を進めます。預金口座や不動産、売掛金などの資産状況が調査され、差し押さえに適した財産が選定されていきます。
法人税の滞納が続くと、税務署は滞納している法人税を回収するために財産差押えを行います。差し押さえは滞納処分の中核をなす強制執行手段です。
差し押さえの対象となる財産は、法人名義の預貯金、不動産、設備、売掛債権などです。
事業継続に必要な財産でも差し押さえの対象となる点に注意しましょう。差し押さえられた財産は換価(売却)され、滞納税金の支払いに充てられます。

法人税を滞納してしまった場合でも、適切な対応によって差し押さえを回避できる可能性があります。詳しく解説しましょう。
期限内に法人税を納付できないときは、できるだけ早く税務署へ相談しましょう。早期の相談は誠意を示すことにつながり、対応の余地が広がります。
相談により、財産の売却を待ってもらうことや納税の猶予(原則1年以内)といった猶予措置が利用できる可能性も。一時的な資金難であれば、これらの制度を活用して立て直しを図れます。
猶予制度を利用するには一定の要件があり、該当しなければこれらの措置は受けられないため、早期の相談が必要です。
税務署に対して、現在の経営状況や資金繰りを説明し、分割納付の相談をすることで差し押さえを回避できるかもしれません。滞納税金を一括で支払えない場合の現実的な選択肢です。
分割納付の交渉では、具体的な返済計画を提示し、誠意をもって対応するのが重要です。実現可能な返済計画と将来の改善見通しを示せれば、交渉が成功する可能性が高まります。
税務署との交渉で分割納付が認められれば、一時的な資金不足でも差し押さえを回避しながら計画的に納税できます。約束した分割納付を確実に履行し、信頼関係を構築するのが大切です。
法人が負担する税金はさまざまですが、滞納が生じるときには消費税や源泉徴収税など預かり金的性質の税金を優先的に支払うべきです。法的責任の重さに違いがあるというのがその理由です。
消費税は消費者から預かっている税金であり、支払えないことが差し押さえのきっかけになりやすいため優先して納付しましょう。滞納した場合の処分が厳しく、経営者の個人的責任も問われるかもしれません。

法人税の滞納中であっても、活用できる資金調達方法はいくつか存在します。わかりやすく説明しましょう。
ファクタリングは企業が保有する売掛債権を売却して現金化できる資金調達方法で、税金滞納中でも利用できる可能性があります。融資ではなく債権売買の形態をとるため、信用情報の影響を受けにくいというのが特徴です。
ファクタリングは融資と異なり、企業の財務状況や信用力よりも売掛金の質に重点を置いて審査されるため、税金滞納中の企業でも利用できる可能性が高いです。審査期間は融資と比較して短く、最短数時間から数日で資金を調達でき、納税資金の確保に役立ちます。
消費者金融や信販会社などのノンバンクのビジネスローンは、銀行融資に比べて審査が早く、納税証明書の提出を求めないことも多いです。銀行ほど厳格な審査基準を設けていない場合があります。
ビジネスローンの審査では信用情報が確認されますが、税金の滞納状況は信用情報に登録されないため、税金滞納中でも審査に通るかもしれません。ただ、ビジネスローンは銀行融資より金利が高いため、まず税金滞納を解消するために借り入れ、その後銀行融資に切り替えるという戦略も有効です。
法人所有の不動産を担保にした融資は、税金滞納中でも資金調達できる可能性があります。担保価値があれば信用状況が多少悪くても融資を受けられるかもしれません。銀行で納税資金の融資を断られた場合でも、不動産担保ローンを扱う金融機関であれば、事業計画書の提出と資金計画のヒアリングにより借り入れできるケースも。
法人税の滞納は延滞税の発生から始まり、督促・催告を経て財産の差し押さえに至る可能性があります。社会的信用の低下や事業継続への影響も大きいため、早期の対応が不可欠です。
差し押さえを回避するには税務署への早期相談と納税猶予制度の活用、分割納付の交渉が効果的です。資金調達方法としてはファクタリング、ノンバンクローン、不動産担保ローンなどの選択肢がありますので、状況に応じた適切な手段で納税資金を確保しましょう。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。