現在掲載中の企業73件

中小企業や個人事業主が経営を続ける上で、資金繰りは常に重要な課題です。大企業との取引時に目にする「期日現金」という決済方法は、資金繰りに大きな影響を与えることがあります。期日現金の仕組みや特徴を理解し、自社の経営にどう影響するのか把握しておきましょう。
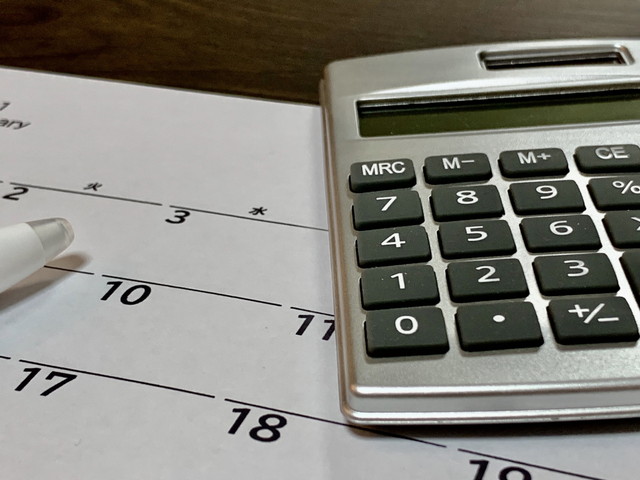
期日現金は日本の商取引で見られる独特の決済方法で、多くの中小企業が直面する課題となっています。経営を継続するために必要な資金繰りに影響を与えるため、正確な理解が重要です。
期日現金は売掛金の決済方法の一種で、通常の支払期日を先延ばしにした取引です。一般的な取引では「翌月末払い」などの比較的短い決済サイクルが採用されるのに対し、期日現金では支払いまでの期間が大幅に延長され、現金で支払われます。
締め日から90日、120日などの長いスパンが取られることが多く、受け取る側の中小企業にとっては資金回収の遅れを意味します。企業規模や交渉力によって条件は異なりますが、基本的には支払う側に有利な条件設定です。
支払期日の延長により、支払側企業は一時的に資金繰りの改善を図ることが可能です。
資金の流出タイミングを遅らせることで、手元資金をより長く保持できるため、大企業にとって魅力的な決済方法となります。
手元資金が少ない時期や大型投資を控えている場合に有効な手段です。キャッシュフローの安定を保ちやすくなり、中小企業にとって特に重要な意味を持ちます。支払い側にとってはメリットが大きい一方で、受け取り側の中小企業は長期間の資金繰り対策をしなければなりません。
振込との違いは、支払いまでの期間の差が大きな点です。通常の振込は締め日から比較的短期間で支払われますが、期日現金では支払期日が大幅に延長されます。
手形決済との違いは、有価証券を発行しない点です。手形決済では紙の証券や電子記録債権が発行されますが、期日現金では単に支払期日が延長されるだけで、債権を表す証券は発行されません。
でんさい(電子記録債権)との違いは、期日前に金銭債権が発行されない点です。でんさいでは電子記録債権として債権が流動化できますが、期日現金では単なる約束に過ぎず、期日前に現金化する手段が限られています。

期日現金による決済は、取引の両当事者にそれぞれ異なる影響を与えます。支払側と受取側で大きく異なるメリットとデメリットを把握し、自社の経営状況に合わせた判断が必要です。
支払期日の延長により、企業の資金繰りに大きな影響を与えます。支払側企業にとっては、支払いを遅らせることで手元資金を確保でき、その間の運転資金として活用できる利点があります。
一時的な資金不足を回避でき、キャッシュフローの安定を保ちやすくなるでしょう。特に季節変動のある業種や成長期の企業にとって、資金繰りの安定は経営の継続性を高める重要なポイントでしょう。
売上の回収と支払いのタイミングのずれを調整できる点も魅力です。多くの企業では売上金の回収と仕入れ代金の支払いにタイムラグが発生しますが、期日現金によりそのギャップを埋めることができます。
手形の発行や管理にかかる事務コストを大幅に削減可能です。手形取引では発行から保管、期日管理まで多くの事務作業が発生しますが、期日現金では単に支払期日を延長するだけなので、事務負担が軽減されます。
印紙代、郵送料、保管コストなどが不要になり、経理部門の業務効率化につながります。手形の場合、額面に応じた印紙税が必要ですが、期日現金では不要となるため、取引金額が大きくなるほどコスト削減効果は高まるでしょう。
取引量の多い企業にとっては特に大きなメリットとなります。数百件、数千件という多数の取引がある大企業では、手形管理の手間とコストの削減が経営効率化に直結します。
法的拘束力が弱く、支払優先度が低いため、債権回収リスクが高まるといわざるをえません。
手形とは異なり法的な裏付けが弱いため、支払側企業の資金繰りが悪化した場合に後回しにされやすい傾向があります。
支払遅延が発生してもペナルティは少なく、受取側企業にとってはリスクが増大します。手形不渡りのような信用情報への影響が少ないため、支払遅延に対する抑止力が弱い点は大きな欠点といわざるをえません。

期日現金の取引は、下請法(下請代金支払遅延等防止法)との関連で法的制限を受ける場合があります。適切な取引条件の設定には、下請法の理解が不可欠です。
資本金3億円超の親事業者と、資本金3億円以下の下請事業者での取引は、製造・修理委託の場合に下請法の適用対象となります。また、情報成果物作成や役務提供の委託では、資本金5,000万円超の親事業者と5,000万円以下の下請事業者が対象となります。
上記条件に該当する取引では、期日現金が適用できません。下請法の適用対象となる取引では、支払期日が60日以内と定められており、それを超える支払期日設定は法令違反となります
下請法が適用される取引では、商品サービスを受け取った日から起算して60日以内に支払う必要があります。納品日を基準として60日を超える支払期日の設定は認められず、違反した場合は是正指導の対象となります。
60日を超える支払期日の設定は法令違反となるため注意が必要です。多くの期日現金取引では90日や120日といった長期設定が見られますが、下請法適用取引ではそうした長期設定は認められません。
下請法に違反する取引を強いられる可能性がある場合、取引を辞退することも検討すべきでしょう。法令違反となる取引条件の受け入れは、将来的なトラブルの原因となる可能性があります。
法的に定められた条件に該当する取引では期日現金が適用できないため、確認が求められます。自社と取引先の資本金規模や取引内容を確認し、下請法の適用有無を正確に判断することが重要です。

期日現金による取引にはさまざまなリスクが伴いますが、適切な対応策をとることでリスクを最小化できます。自社の経営状況を見極めながら最適な対応を選択しましょう。
ビジネスの発展や新しい市場への進出など、将来的に有益な可能性がある取引か検討が必要です。短期的には資金繰りに負担がかかっても、長期的な事業拡大につながる取引であれば受け入れる価値があるかもしれません。
入金されるまでに経営を回せるほどの資金があることが前提条件です。期日現金の長期サイトに耐えられる資金力がなければ、取引自体を見直す必要があります。自社の資金繰り状況を冷静に分析することが大切です。
「毎月末日締め、翌月25日払い」など、60日以内の支払期日設定が望ましいとされます。下請法の規制に関わらず、できるだけ短期間での支払いサイクルを交渉することで、資金繰りの安定化を図ることができます。
「毎月末日締め、翌々月25日払い」など、60日を超える可能性がある設定は避けるべきです。月によって日数が異なるため、一見60日以内に見える設定でも実際には60日を超える場合があり、注意が必要です。
代替手段としては、ファクタリングなど、他の資金調達方法の活用を検討することも有効です。期日現金による長期の入金待ちが経営を圧迫する場合、売掛債権を早期に現金化する手段として、ファクタリングの利用が選択肢となります。
専門家への相談を通じて、最適な決済方法や資金調達方法を選択することが望ましいです。顧問税理士や金融機関に相談し、自社の経営状況に合った資金調達手段を検討すると良いでしょう。
期日現金は通常の支払期日を延長した決済方法で、支払側企業の資金繰り改善に役立つ一方、受取側企業には資金回収の遅れというリスクをもたらします。特に資本金規模の差がある取引では、下請法の適用により60日以内の支払いが義務付けられており、法令遵守の観点からも注意が必要です。
企業経営において期日現金のリスクに対処するには、取引の価値を慎重に判断し、適切な支払期日の設定交渉を行うことが重要です。状況によってはファクタリングやでんさいなどの代替手段も検討し、自社の資金繰りを安定させる工夫が求められます。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。