現在掲載中の企業73件
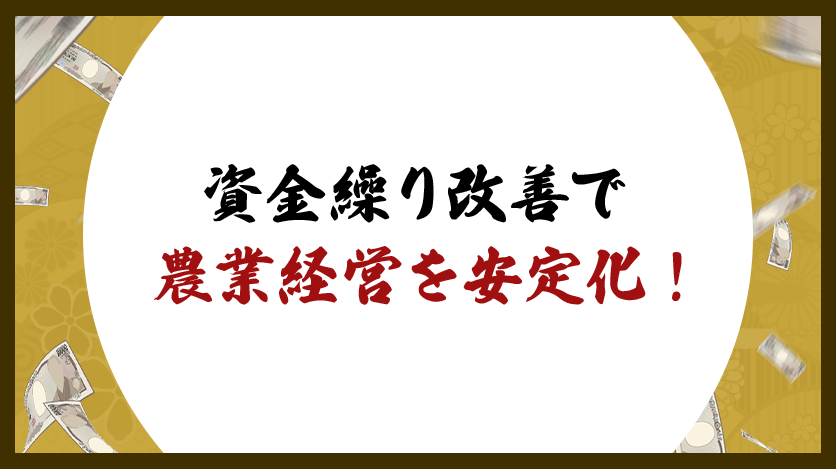
毎年の作付けから収穫に至るまで、運転資金や設備投資など、多額の資金が必要になるのが農業経営です。そんな農業経営を安定化させるには、「資金繰り」が重要になります。
本記事では、資金繰りの重要性から、すぐに役立つ具体的な改善策まで、実践的な内容を解説します。農業経営をより安定化させるためにも、ぜひ参考にしてください。

ひとくちに農業経営と言っても、実態は一般企業とは異なります。特に近年は、資材の価格高騰や、気候変動の影響で収穫量が読めなかったりと、収入が安定しづらい傾向にあります。こうした理由からも「資金繰り」は、経営の命綱と言っても過言ではありません。
農業には特有の「季節性」があります。収穫が終わるまでは支出が続く一方で、収入が発生するのは収穫の後です。
さらに、天候に左右される不安定さもあります。最近は異常気象が増えていて、予定していた収穫ができないリスクも高まっています。
初期投資の規模が大きいのも、農業経営の特徴です。農地取得、ハウス建設、トラクターといった農業機械購入など、事業を始める段階でかなりの資金が必要となります。
もし資金繰りがうまくいかなければ、必要な肥料や農薬、種苗などの購入が滞ります。適期の作業ができず、収穫量の低下へと繋がるでしょう。肥料価格の高騰により、必要量を確保できない農家の増加は深刻な問題です。
設備の修理や買い替えが遅れることで、作業効率が低下する可能性があります。生産性の悪化は経営難に直結します。毎日使う農業機械は、故障のリスクを常に伴うものです。
人手不足が深刻な農業では、従業員を確保するのにも資金が必要です。給与の支払いが遅れたり、福利厚生を削らざるを得なくなると、離職率が増加します。
借入金の返済が滞ると、新規の資金調達はさらに難しくなってきます。信用力の低下にも繋がり、取引そのものに影響を及ぼしかねません。

資金繰りが悪化する理由は、大きく分けて「外部環境」と「内部管理」の問題に分けられます。例えば、天候や市場価格の変動、資材価格の高騰といった外部要因は、個人ではなかなかコントロールしにくい部分です。とはいえ、一切対処ができないわけではありません。資金繰りに困ったときは、まず原因を正確に把握することから始めましょう。
収量が思ったより少なかったり、市場価格が下がったりして、計画通りの売上が確保できないケースが増えています。特に近年は気候変動の影響で、収量を安定させるのが難しいとされています。
市場価格は、需給バランス次第で大きく変動します。豊作で供給が多くなると価格が下がり、その結果収入が減る可能性があるだけでなく、輸入農産物との競争もあり、市場価格は大変揺らぎやすいです。
ここ数年、肥料の値段がどんどん上がっています。世界的な需給の影響もあって、資材費が高騰しているのです。直接的に利益を圧迫するだけでなく、資金繰りを悪化させる要因となっています。
人手不足を背景に、人件費の上昇も歯止めがききません。パートタイム労働者の時給も上がっており、こちらも節約しようがないため、経営に大きな負担をかけています。
燃料費の変動も見逃せません。農業機械の燃料やハウス栽培の暖房用燃料など、その費用の上昇は、経営者にとって耳が痛い話です。
売掛金回収の遅れは、資金繰りの難易度を一気に押し上げます。
取引先の支払サイトは長期化する傾向にあり、運転資金の確保が課題です。
日々の収支管理が甘いと、急な出費への対応も難しくなります。特に、収支計画が現実に合っていないと、必要なタイミングで資金を用意できないため、適切な収支バランスを維持する必要があります。

農業経営では、事業の特性に合った資金調達方法を選べるかが重要です。
公的支援制度から民間金融機関による融資まで、選択肢はたくさんあります。経営状況や資金の使い道に応じて、適切な資金調達方法を選びましょう。
日本政策金融公庫は、農業者向けに各種融資制度を用意しています。新しい農業技術を取り入れる際に利用できる農業改良資金、規模を拡大したり設備投資に対応できるスーパーL資金などがあります。
JAバンクでは、農業者に寄り添った融資を実施しています。身近な資金調達手段の1つで、地域密着型の支援も期待できるでしょう。
また銀行や信用金庫など、民間金融機関の融資制度も活用できます。審査の基準は厳しいものの、事業計画の実現可能性についてのアドバイスが期待できます。
農業次世代人材投資資金は、新規就農者の経営確立を支援する制度です。最長5年間の給付により、経営の安定化をサポートします。
青年等就農計画に基づく支援制度は、経営発展に必要な機械・施設の導入を後押ししてくれます。この制度は、特に地域農業の担い手育成に貢献します。
環境保全型農業直接支払交付金は、環境に配慮した営農活動を支援します。持続可能な農業経営の実現に向けた取り組みを応援しています。
最近では、クラウドファンディングという選択肢もあります。商品開発や設備投資の資金を消費者から直接募る方法です。明確な資金使途を提示することがポイントです。
また、ファクタリング(売掛債権買取)という、売掛金を早期に現金化する手法も注目されています。資金繰りの改善に即効性があるのが魅力の資金調達方法です。


資金ショートを防ぐには、計画的な資金管理が不可欠です。収支予測を立て、それにあわせた資金確保はもちろん、収益改善も必要になってきます。ここでは、農業経営で資金ショートしないための対策について、いくつかご紹介します。
資金繰り表を作ることで、経営状況を細かく把握できます。月次での収入支出予測、借入金返済スケジュールなど、資金の動きを可視化することで、資金ショートを大幅に防ぐことができるでしょう。
また、収支予測は営農計画と連動させましょう。作付計画から必要経費を積算し、収穫時期の売上予測を組み込んだ計画策定をするのが重要です。
資金不足の兆候は、とにかく早く発見することです。
初期対応が決め手となる場合が多いので、即座に気づけるようになるためにも、資金繰り表は欠かさずチェックしましょう。
収益を上げる対策として、 有機栽培やブランド化など、付加価値を提供するのは良い方法です。市場価格に左右されにくいというのは、大きな強みとなるでしょう。
また、直売所運営やインターネット販売により、 販路を広げることもおすすめです。市場に頼りすぎない経営を拡大することで、資金ショートが防げます。
ロボットやAIを活用した スマート農業の導入は、生産性の向上に大きくつながります。ICT技術活用により労働生産性が上がり、コスト削減と収益向上の両方が実現できる可能性があるでしょう。
資材の共同購入や、農業機械の共同利用も、コスト削減には効果的です。複数人でシェアすることで、初期投資を抑えることができます。
省力化技術の導入もひとつの手です。作業効率が良くなるので、人件費を削減することもできます。農作業にかかる手間を減らすことで、経営の負担も軽くなるでしょう。
経営の規模は、収支バランスをきちんと考慮して決定します。設備投資が大きすぎると固定費が増え、逆に経営が苦しくなることもあるので注意です。
資金繰りの改善は、経営を続けていく上で欠かせません。収入が天候に左右されたりする、農業ならではの課題もあります。公的支援制度をうまく活用したり、自分に合った資金調達方法で、収支管理を徹底しましょう。いざというときは専門家に頼るのも手です。
急に資金が必要になったときには、売掛金を早めに現金化できるファクタリングがおすすめです。資金繰りを改善し、農業経営を安定化させましょう。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。