現在掲載中の企業73件
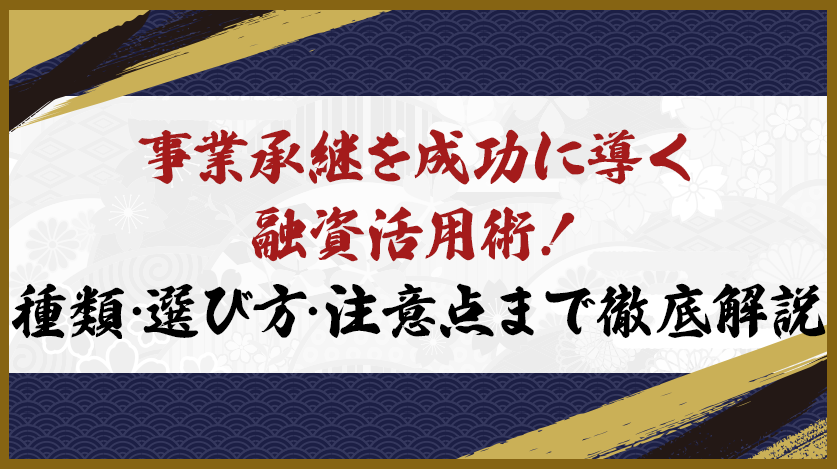
中小企業の世代交代は、企業の未来を決定づける大きな節目と言えます。ところが、資金を十分に準備できずに、やむを得ず廃業へ追い込まれる例も後を絶ちません。こうした事態を回避し、後継者が安定して経営を引き継ぐようにする上で、融資の活用が欠かせません。
そこで本記事では、事業承継時に検討すべき融資の特徴や、審査を通るための対策、活用すべき支援制度などを詳しく解説していきます。

事業を順調に運営していても、後継者が株式を買い取る費用や新しい設備を導入するための費用、さらに相続税の納付資金など、多額の資金需要が一度に押し寄せることが珍しくありません。こういった資金を自己資金のみで賄うのは難しいため、金融機関の融資を上手に組み合わせることが、事業承継の成功につながります。
事業承継とは、会社の経営権や資産、技術、ノウハウなどを次世代に継ぐことです。
近年は経営者の高齢化が進み、65歳以上の経営者が全体の3割を超える状況となっています。
後継者不在率は6割程度にも達しており、現社長の引退に合わせて休廃業せざるを得なくなる企業が増えているのが実情です。こうした状況を避けるためには、早い段階から継承準備を進め、必要な資金調達手段を整えることが極めて重要です。
事業を引き継ぐ際は、株式の買取費用や設備投資費、運転資金、さらに相続税の納付など、多額の資金需要が一度に発生します。自己資金ではまかなえず、金融機関の支援も受けられず、最終的に廃業を選択せざるを得ないといったケースが増加中です。
こうした事態を回避するには、早い段階から金融機関との連携を図り、必要額を正確に算出しておくことが欠かせません。
たとえ経営が順調な企業であっても、承継時の資金不足が原因で、後継者が新しい施策を打ち出せないまま経営が停滞、やむを得ず事業を畳む場合も見受けられます。
一方で、融資を上手に活用できれば、承継後の経営はもちろん、設備投資や人材強化など今後の成長戦略にも前向きに取り組めるでしょう。
後継者の経営スキルを育てるには、「人材育成」が欠かせません。時間はかかってしまいますが、後継者の準備が次世代の経営を安定させる土台になります。
また、 数字を用いて将来像を示す「事業計画」があれば、金融機関や従業員からの協力を得やすくなります。特に融資の審査では、計画が具体的であるほど有利に働くでしょう。
さらに、 「資金調達」の検討も早めに行い、金融機関や専門家と連携を深めることが大切です。複数の調達方法を比較して最適な組み合わせを見つければ、承継後の経営もスムーズに進められるでしょう。

融資先としては、都市銀行・地方銀行・信用金庫などの民間金融機関や、日本政策金融公庫といった公的機関が代表的です。審査基準、金利、担保の要否などが異なるため、事業規模や財務内容に合わせて選ぶとよいでしょう。
都市銀行は高額融資に対応しやすく、金利も比較的低い場合がありますが、担保や保証人を厳しく求められがちです。一方、信用金庫や地方銀行は地域に根ざしているぶん、融通が利きやすい反面、大きな金額の融資には不向きな場合があります。
信用力が不足する企業でも融資を受けやすくする仕組みです。株式の買取や設備投資など、多額の費用が必要な事業承継では大きな助けになりますが、保証料という追加コストが発生する点に注意が必要です。
長期かつ据置期間が設けられるなど、事業承継向けの融資制度があります。金利は民間よりやや高めのこともありますが、担保や保証人が不要のメニューもあり、他の支援策と組み合わせれば新規事業や資金繰りにも活用できます。
| 項目 | 民間金融機関 | 政府系金融機関 | 信用保証協会 |
|---|---|---|---|
| 機関例 | 銀行、信用金庫 | 日本政策金融公庫 | 各都道府県の信用保証協会 |
| 金利 | 比較的高い | 比較的低い | – (保証料が必要) |
| 融資限度額 | 高い | 中程度 | 中程度 |
| 返済期間 | 短期〜長期 | 長期 | – (保証する融資による) |
| 審査基準 | 厳しめ | やや緩やか | – (保証する融資による) |
| メリット | 迅速な融資、 多様な商品 | 低金利、長期融資 | 担保・保証人不要 |
| デメリット | 金利が高い、 審査が厳しい | 審査に時間がかかる | 保証料が必要、 審査に時間がかかる |
| その他 | 経営支援にも力を入れている | 金融機関の融資を保証 |

融資には審査があり、承継後も返済義務が続きます。そのため、必要書類の準備や将来の資金繰り予測をしっかり行い、金融機関に対して信頼感を示すことが不可欠です。後継者が経営者として相応の知識や経験を持つことも、審査時に有利に働きます。
金融機関が特に重視するのは、返済能力の有無です。具体的には、直近3期ほどの決算書を見て、売上高や利益率、自己資本比率などの数値を確認します。その上で、 事業承継後の経営見通しをどの程度具体的に示せるかが、審査の重要なポイントになるでしょう。
後継者が 経営者として、どのような素養や経験を持っているかも審査対象です。例えば、長年営業職を担当していて、取引先との信頼関係を築いている、経営に必要な資格や研修を受けているといった事実があれば、融資実行の可能性は高まります。
借入額が年商を大きく超えていると審査が通りづらくなる傾向があるため、必要資金を算出する段階から注意が必要です。
融資を受ける以上、毎月あるいは毎期の返済が滞らないよう、資金繰りを管理しなければなりません。事業承継の直後は組織再編や新規設備への投資など、意外な出費が重なることもあります。返済と事業運営のバランスを誤ると、経営が一気に苦しくなるので注意が必要です。月々のキャッシュフローを可視化しながら、返済可能な上限を慎重に見極めましょう。
事業承継を機に融資を受ける場合は、できるだけ早い段階から金融機関に相談を持ちかけるのが理想です。承継の2年前くらいには話を始め、必要書類の準備や事業計画のブラッシュアップを行いましょう。
決算書だけでなく、経営計画書、資金計画書、場合によっては後継者の経営方針を示す書類を求められることがあります。
担保や個人保証をどうするかについても、事前にしっかり打ち合わせをしておくべきです。特に事業用資産と個人資産が混在している場合や、後継者が個人保証を引き継ぐかどうかでトラブルになることもあります。専門家のサポートを受けることも検討しながら、後継者の負担が過度に重くならないよう注意してください。

公的支援制度の活用で、事業承継時の資金負担を軽減できます。相談窓口や専門家の力を借りることで、税務や法律の面でも適切なサポートを受けられるでしょう。
事業承継税制とは、事業承継時の相続税や贈与税の負担を軽減する制度です。
中でも、特例事業承継税制の実施期限は、法人が2027年12月31日、個人事業主は2028年12月31日であり、期限があるため注意が必要です。ただし、利用時には雇用を一定数確保するなどの要件があり、専門家のアドバイスが不可欠です。
事業承継補助金は、中小企業が事業承継やM&Aを機に経営革新に取り組むときに活用できる制度です。最大600万円が支給されることもあり、新製品の開発や販路拡大などの投資に使えます。各都道府県の産業支援センターでも独自の助成制度を設けているところもあるので、地元でどのような支援を受けられるのかを早めに調べるとよいでしょう。
銀行や信用金庫は融資相談に加え、事業承継全般についてアドバイスしてくれる場合があります。最近ではM&Aマッチングや後継者育成プログラムなど、幅広く対応してくれます。
各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターでは、無料で事業承継診断や専門家派遣を実施しています。商工会議所や中小企業団体中央会なども、会員向けに各種支援サービスを行っています。
また、税理士や公認会計士は税務・会計面に関するアドバイスをもらうことが可能で、弁護士は契約書の作成や法的リスク管理で力を発揮してくれるでしょう。
事業承継は企業の未来を左右する重大な局面です。後継者育成や事業計画、融資・公的支援制度の活用など、早期から準備を進めれば、スムーズな交代と持続的発展が可能になります。これまで培った技術や信頼を次世代へ継ぐためにも、計画的に対応していきましょう。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。