現在掲載中の企業73件
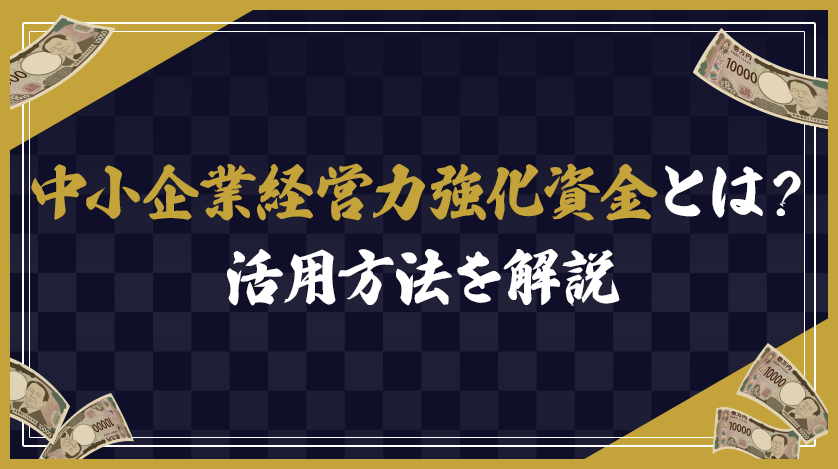
経営基盤の強化に向けて資金を確保することは、中小企業の成長を左右する大きな要素です。日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」は、その名のとおり経営力を高めたい事業者を支援する融資制度で、最大7億2千万円まで利用できる枠が用意されています。
設備投資や運転資金など、幅広い用途に対応しているため、経営改善はもちろん、新規事業や人材育成への投資など、さまざまな場面で活用が可能です。
本記事では制度の概要から申込手順までを詳しく紹介します。

「中小企業経営力強化資金」は、日本政策金融公庫が扱う融資制度の一つで、経営の将来性や経営者の人柄・資質などを重視して審査する点が特徴的です。
創業間もない時期の企業でも申し込みやすく、金利が融資実行時点で固定されるため、金利変動リスクを抑えつつ長期返済ができるという利点があります。
中小企業経営力強化資金の対象は、「中小企業基本法」に準拠した企業が中心となります。
製造業なら資本金3億円以下あるいは従業員300人以下、卸売業なら資本金1億円以下あるいは従業員100人以下が対象です。小売業なら資本金5千万円以下あるいは従業員50人以下、サービス業なら資本金5千万円以下あるいは従業員100人以下という要件が定められています。
個人事業主であっても、事業の規模や業種によっては申し込める場合があるため、まずは自社の状況が要件に合致しているか確認が必要です。
対象となる資金使途は広く、工場や店舗の建設・改装費用、機械設備の導入費用、販路開拓の広告宣伝費や人材育成費用などが挙げられます。
さらに研究開発費用や海外進出に関連した投資、事業承継に伴う費用なども認められるため、自社の具体的な戦略にあわせて柔軟に活用しやすい点が魅力です。
融資の返済条件は資金使途によって異なります。
設備投資向け融資なら最長20年以内・据置期間は2年以内、運転資金向け融資では最長7年以内・据置期間は2年以内が基本です。
長期返済が可能なうえに金利は融資実行時点で確定するため、月々の返済額を予測しやすく、事業計画を立てやすいでしょう。
返済方式は主に元金均等返済で、毎月の返済額が一定になるよう調整されています。
特定の要件を満たした事業者の場合は特別金利が適用され、少し低めの金利で借りられる場合もあります。
経営革新計画の承認を受けた企業や、特定地域で事業を営む企業は、優遇措置の対象となる場合があるため、自社が該当するかどうか事前に確認してみましょう。
担保の要否は、融資希望額や企業の財務状況などを踏まえて判断されます。
保証人については、経営権を実質的に握っている代表者が個人保証するケースが大半で、第三者の保証を加えるかどうかは状況次第です。とはいえ、個人保証を回避したいと考える経営者も多いため、事前に専門家へ相談しながら、どのような担保や保証設定が必要かを検討することをおすすめします。

中小企業経営力強化資金は、創業間もない企業でも利用できる点や、自己資金要件が定められていない点など、制度上の強みが複数あります。
しかしながら、申し込みから融資実行までに時間がかかる場合もあるほか、書類作成や認定支援機関とのやり取りといった手続き面の負担が生じます。以下では主なメリットとデメリットについて、もう少し掘り下げて解説します。
一般的な融資制度だと「創業○年以上」といった実績要件や、総事業費の一定割合を自己資金でまかなう必要があるなど、ハードルが設けられていることが多いです。
ところが本制度では、創業直後でも可能性があり、自己資金については可能な限り準備することで審査が有利になるものの、定められた要件はありません。事業計画に説得力があれば、資金の苦しい中小企業や個人事業主でも、大きな額を借りられるチャンスがあります。
また、金利が固定される上、最長20年という長い期間で返済できるのは大きなメリットです。金利変動によるリスクを避けつつ、大型投資や長期的な成長戦略を落ち着いて進められるでしょう。担保や保証人の要件も、民間の銀行融資に比べると比較的柔軟に判断される場合があるため、不動産など大きな資産を持たない企業にとって利用しやすい制度です。
一方で、認定支援機関(認定経営革新等支援機関)との連携が必要になる点は、検討が必要です。事前に相談したり、事業計画書を一緒に作成するなど、手厚いサポートを得られる反面、時間と手間がかかるデメリットがあります。
また、日本政策金融公庫の指定する書式を使った事業計画書の作成や、融資実行後の定期報告が必要になる点も考慮すべきでしょう。市場分析や競合調査、具体的な売上予測など、書類作成は詳細かつ綿密な内容が求められます。もし経営者が忙しく、書類作成に割ける時間が限られている場合には、外部の専門家を活用するなどの工夫が必要です。
さらに、融資金利が他の公的制度ほど大幅に低下するわけではないケースもあるため、信用保証協会の保証付き融資など、他の制度も含めて総合的に検討するのが望ましいでしょう。

申し込みから融資実行までの流れは以下の通りです。この流れを理解していないと、スケジュールを誤って事業計画が滞る恐れがあります。
特に認定支援機関とのやり取りや、公庫側からの追加書類要請を受けて計画を修正する作業は時間を要する場合があるので、できるだけ早めに動き出しましょう。
日本政策金融公庫へ相談し、企業概要や資金使途、希望する融資額を伝えます。最近は電話やウェブサイトからの問い合わせにも対応しているため、最寄りの営業店へ行く余裕がなくても相談は可能です。
必要書類は法人の場合、直近3期分の決算書、会社の登記簿謄本、定款、試算表などが基本となります。個人事業主の場合は確定申告書や青色申告決算書などが求められます。設備投資が目的の場合は見積書や工事計画書なども忘れず用意しましょう。
同時並行で、認定支援機関に事業計画書作成のサポートを依頼することになります。計画書には事業の概要、強み、ターゲット市場、売上予測、設備計画、資金計画など多岐にわたる項目を盛り込み、根拠のある数字で説得力を示す必要があります。
提出書類が揃ったら、まず書類審査が行われ、事業計画の実現可能性や返済能力が中心的に確認されます。売上や利益率だけでなく、業界動向や競合他社との優位性など、経営戦略が具体的に示されているかも見られます。
書類審査を通過すると、面談を含む実態調査が行われる場合があります。公庫の担当者が企業の現場を訪問し、経営者の方針や設備の状態、従業員の雰囲気などを把握することも珍しくありません。この現地調査での印象や、経営者の熱意・人柄などが判断材料となるため、日常の管理体制を整え、質問には正直かつ的確に答えることが望ましいです。
また追加資料の提出や計画の修正を求められることもあり、余裕を持ったスケジュール設定が望ましいでしょう。
融資決定後は金銭消費貸借契約の締結に進みます。契約内容には融資金額や金利、返済条件だけでなく、期限の利益喪失事由など多岐にわたります。
契約締結後、融資実行までは通常1~2か月程度かかります。ただし案件の複雑さや書類の準備状況によって期間はかわるため、事業計画上、資金が必要となる日に余裕を持って申し込みを行いましょう。特に設備投資などで、工事や機器の納期が迫っている場合は、早め早めの準備がトラブルを回避するうえで不可欠です。
中小企業経営力強化資金は、創業初期や資金繰りが厳しい企業でも比較的大きな額の融資を受けやすく、長期・固定金利で返済できる点が魅力です。事業拡大や経営革新、事業承継など、将来を見据えた投資を検討している方にとっては有力な手段と言えるでしょう。
ただし、認定支援機関とのやり取りや事業計画書の詳細な作成、審査時の追加資料提出など、手続き面でのハードルは決して低くありません。制度の特徴を理解したうえで、自社の状況に合わせて活用を検討することをお勧めします。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。