現在掲載中の企業73件
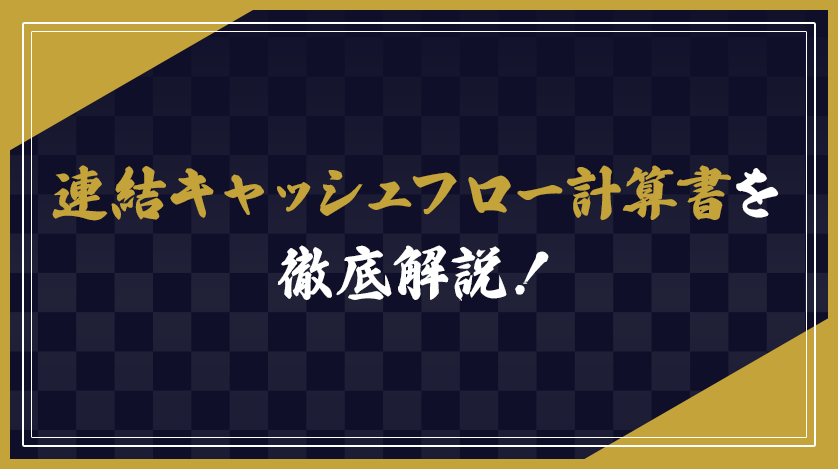
資金繰りで悩んでいる経営者の方は多いのではないでしょうか?経営者にとって、資金繰りを改善するためにも決算書類を読み解く力は必要不可欠です。本記事では、経営判断に欠かせない「連結キャッシュフロー計算書」について、基本から詳しく解説します。

中小企業でも、子会社や関連会社を持つことが増えています。グループ経営における資金の流れを把握することは、経営者にとって重要な仕事です。ここでは、経営者の立場から見た連結キャッシュフロー計算書の基礎知識について解説します。
経営する会社に子会社や関連会社がある場合、各社の資金繰りを個別に見るだけでは不十分です。グループ全体としてどれだけの現金が入ってきて出ていったのかを把握する必要があります。連結キャッシュフロー計算書は、グループ会社全体の現金の動きを一つにまとめた財務諸表です。
一般的なキャッシュフロー計算書は、経営する会社単体の現金の動きしか示してくれません。子会社への支払いも、外部への支払いと同じように「出金」として扱われます。
しかし、連結キャッシュフロー計算書では、グループ会社間での現金のやり取りは相殺されるのです。会社から子会社への支払いは、グループ内での資金移動として扱われるため、グループ外部との取引だけが表示されます。
そのため、企業グループとしての実質的な資金力を把握できるという利点があります。
銀行や投資家は、経営者が運営するグループ全体の経営状態を重視します。連結キャッシュフロー計算書は、 グループ全体としての資金創出能力を示す重要な基準となるでしょう。
また融資を受ける際、銀行は返済能力を細かく調査します。連結キャッシュフロー計算書で良い数値を示せれば、 有利な条件での借入も見込めるでしょう。
さらに経営者としても、グループ全体の資金繰りを把握することで、 より戦略的な運営が可能となります。子会社への投資判断や、グループ内での資金配分にも活用可能です。

連結キャッシュフロー計算書は、営業、投資、財務の3つの区分で構成されています。それぞれの活動別に現金の動きを把握することで、グループ経営の実態が見えてくるでしょう。各区分の意味と重要性について、実態に即して説明していきます。
営業活動によるキャッシュフローは、商品販売やサービス提供など、本業での活動による現金の増減を表します。
例えば、売上代金の回収や仕入代金の支払い、従業員給与の支払いなどです。グループ全体として本業でどれだけの現金を生み出せているかを示す重要な指標です。
営業活動によるキャッシュフローがプラスであれば、本業で十分な現金を生み出せていることを意味します。マイナスが続く場合は、収益構造の見直しが必要かもしれません。
投資活動によるキャッシュフローは、設備投資やM&A(企業の合併・買収)など、将来の成長に向けた投資による現金の増減を表します。
例えば、工場や機械設備の購入、子会社株式の取得などです。
将来の成長に向けて積極的に投資をしているため、通常はマイナスになるケースがほとんどです。ただし、マイナス幅が大きすぎる場合は要注意です。営業活動で得た現金以上の投資は、財務的な負担となる可能性があります。
財務活動によるキャッシュフローは、借入金の調達や返済、増資による資金調達、配当金の支払いなど、資金調達に関連する現金の増減を表します。
財務活動によるキャッシュフローがプラスの場合、外部から資金調達していることを意味し、マイナスの場合は借入金返済や配当金支払いなどで資金流出が発生していることを意味します。

経営者自身が連結キャッシュフロー計算書を理解することはとても大切です。作成方法を知ることで、数字の持つ意味をより深く理解できるでしょう。以下では、連結キャッシュフロー計算書の作成方法と見方についてご説明していきます。
連結キャッシュフロー計算書の作成方法は、直接法と間接法の2つがあります。
直接法は、現金の収入と支出を直接集計する方法です。分かりやすい反面、手間がかかるのが注意点です。
間接法は実務では一般的な方法であり、損益計算書の当期純利益を出発点として、現金の増減を伴わない減価償却費などの項目を調整していく方法です。会計システムを活用すれば、比較的容易に作成できます。
各グループ会社の個別キャッシュフロー計算書を、単純に合計するだけでは不十分です。 グループ会社間の取引を相殺する必要があります。例えば、親会社から子会社への支払いは、グループ全体では現金の移動に過ぎません。
またグループ会社間の取引で発生した利益のうち、 グループ外部への販売が完了していないものは消去しましょう。また、 関連会社の利益や損失は、自分がどれくらい出資しているかに合わせて計算し、正しく調整する必要があります。
当期純利益が高くても、必ずしも現金が増えているとは限りません。売掛金が増加している場合、利益は計上されても現金は未回収の可能性もあります。利益とキャッシュフローの差異を分析することで、実態が見えてくるでしょう。
投資活動については、将来性評価が重要です。高額な設備投資やM&Aは、グループの将来を左右する可能性があります。投資の効果を慎重に見極める必要があります。

子会社や関連会社をどこまで連結するか、判断基準を決めることは重要です。出資比率だけでなく、実質的な支配力も考慮する必要があります。
議決権の過半数を所有していれば、原則として連結対象となります。ただし、議決権を持っている株の割合だけでなく、実際に会社を動かす力も重要です。
取締役会の過半数を指名できる権限や、重要な意思決定に関与できる権限があれば、連結対象となる可能性があります。
定款変更に必要な議決権を保有している場合も、経営の根幹に関わる決定権を持っているため、会社を動かす力があると判断されます。
議決権の過半数を所有していなくても、実権を握る力がある場合は連結対象となる場合があります。例えば、他の株主との契約により、経営の支配権を確保している場合です。
逆に、議決権の過半数を所有していても、破産手続中などで実権を握る力を失っている場合は、連結対象から除外されます。形式的な基準だけでなく、実態に即した判断が必要です。
連結キャッシュフロー計算書は、グループ経営における重要な財務指標です。本業での現金創出能力、投資活動の妥当性、財務活動の健全性を総合的に判断することが可能です。経営者として、グループ全体の資金繰りを把握し、適切な経営判断を下すための重要なツールとして活用してみてはいかがでしょうか。定期的な確認と分析を心がけることで、より強固な経営基盤を築くことができるかもしれません。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。