現在掲載中の企業73件
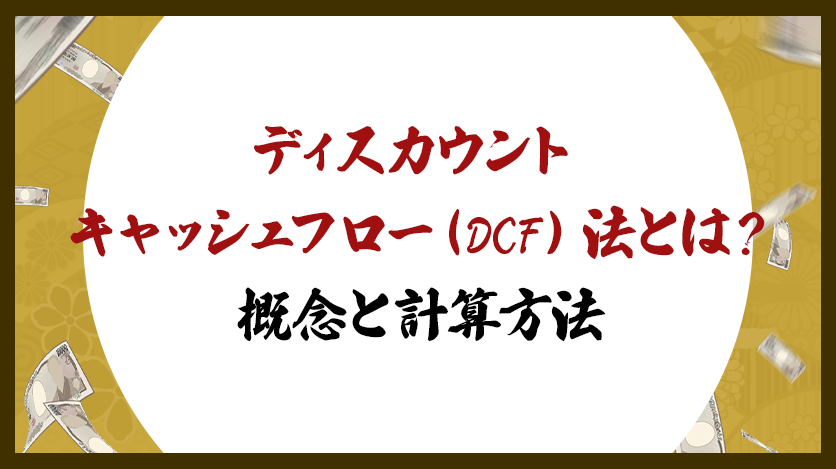
経営者の皆さんは、ディスカウントキャッシュフロー(DCF)法をご存知ですか?
DCF法は、事業価値を算出する代表的な手法として認知されています。
本記事では経営者の視点からDCF法について解説し、実務での活用方法までを分かりやすく説明します。資金繰りに悩む経営者から事業承継を検討する経営者まで、幅広い場面で役立つ知識を提供しますので、ぜひご一読ください。

企業価値を評価する手法は様々存在しますが、その中でもDCF法は特に実践的かつ信頼性の高い方法として、世界中で採用されています。将来の収益予測から、現在の企業価値を導き出すため、経営者が今後の事業展開を考える上で重要な情報になってくれるでしょう。
DCF法は、将来のキャッシュフロー(事業から生み出される純粋なお金の流れ)を現在の価値に換算して評価するというものです。
実際に銀行融資における事業計画書の作成時や、事業承継における企業価値算定の際にも重宝される手法とされています。
まず、DCF法による評価は単なる数字合わせではありません。事業が将来的に継続する可能性や成長性、リスク要因までを包括的に分析できる点が最大の強みです。
また、事業承継を控えた経営者にとって、DCF法は後継者への説明資料としても説得力を持ちます。数値に基づく客観的な評価は、感情的になりがちな承継交渉の場においても、冷静になれる判断材料を提供してくれるでしょう。
DCF法にて評価に用いる要素は主に3つです。
1つ目はフリーキャッシュフロー(企業が自由に使えるお金)で、売上から必要経費や設備投資を差し引いた金額を指します。2つ目は割引率(企業のリスクや借入金利を反映した比率)です。3つ目は割引期間(将来のキャッシュフローを何年分見込むか)になります。
経営者目線で言えば、フリーキャッシュフローは事業の稼ぐ力、割引率は事業のリスク度合い、割引期間は事業の継続性を表現する指標と理解できます。
実際にフリーキャッシュフローを算出する場合は、売上高から変動費、固定費を差し引き、運転資金の増減や設備投資額を考慮しましょう。特に季節変動の大きい業種では、年間を通じた資金繰りの変動も加味しなければなりません。
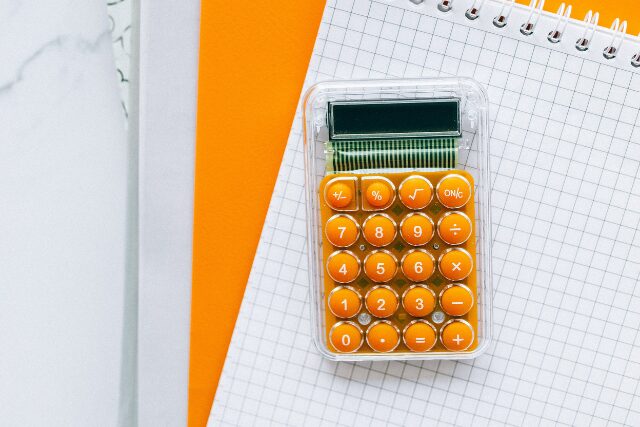
価値評価の信頼性は、限られた情報と経験則を組み合わせながら、現実的な評価を行うものです。以下では、DCF法の具体的な計算手順と実務上の留意点を解説します。
将来キャッシュフローの予測は、過去の実績と今後の事業計画に基づいて行います。具体的には、売上高から原価、人件費、経費などを差し引き、減価償却費や運転資金の増減を加味した上で算出しましょう。
中小企業の場合、業界動向や競合状況、自社の強み弱みを踏まえた現実的な予測が求められます。過度に楽観的な予測は避け、保守的な見方で将来を見据えることが重要です。
また、予測期間は通常5年から10年が一般的です。
ただし、業界の特性や事業サイクルによって適切な期間は変動します。例えば、不動産開発事業では物件の開発期間に応じて、より長期の予測が必要な場合もあります。
割引率は加重平均資本コスト(WACC:借入金利と期待収益率を加重平均した比率)を用いるのが一般的です。中小企業では実務上、借入金利に事業リスクを加味した数値(例:借入金利+リスクプレミアム5~10%)を使用することが多いです。
ただし、業界特性や企業規模、財務状況によって適切な割引率は変動します。景気変動の影響を受けやすい業種ほど、高めの割引率設定が求められます。
なお、設定した割引率は定期的な見直しが必要です。金利環境の変化や事業リスクの変動に応じて、適切な水準に調整することで、精度の高い評価が可能となります。特に長期の事業計画では、経済環境の変化に応じた柔軟な見直しが重要です。
現在価値については、各年度のキャッシュフローを、設定した割引率で換算します。
計算式は「現在価値=将来キャッシュフロー÷(1+割引率)の年数乗」です。
例えば、1年後に100万円のキャッシュフローが見込まれ、割引率が10%の場合、現在価値は約91万円(100÷1.1)となります。この計算を各年度分実施し、合計することで事業価値が算出されます。
残存価値として、予測期間(通常5~10年)以降の価値も考慮しなければなりません。
具体的には、永続的な成長を前提とした定率成長モデルや、予測最終年度のキャッシュフローを基準とした倍率方式などを算出する際に用いられます。
実際に中小企業では、業界平均の利益倍率を用いて残存価値を算出するケースが多く見られます。この際、自社の市場シェアや競争力を加味した適切な倍率設定が重要です。
また、残存価値の算出では、長期的な成長率の設定も重要です。一般的にはGDP成長率や業界の平均成長率を参考に、保守的な数値を採用することが推奨されます。極端に高い成長率を設定すると、評価額が非現実的な水準となってしまうため注意しましょう。

実は企業価値の評価において、完璧な手法は存在しません。DCF法も例外ではなく、実務での活用には両面を理解した上での適切な運用が求められます。以下では、実務経験から得られた知見を交えながら、メリットとデメリットを詳しく解説します。
DCF法の最大の利点は、 事業の将来性を数値で表現できる点です。金融機関への事業計画提出時や、事業承継における後継者説得時に、客観的な根拠として機能します。
また、 投資判断においても、期待収益とリスクを定量的に評価できるため、精度向上に貢献してくれるでしょう。特に新規事業立ち上げや、設備投資について判断する際に効果を発揮します。
さらに、評価過程で得られる気づきも重要な利点です。将来キャッシュフローの予測作業を通じて、 事業の強み弱みや成長機会、リスク要因の把握が可能となります。これらの情報は、経営戦略の立案や見直しにも活用できるでしょう。
DCF法のデメリットとしては、 将来予測の困難さを避けられない点です。特に中小企業は外部環境の影響を受けやすく、正確な予測が立てにくい状況にあります。
予期せぬ事業環境の変化や、競合他社の動向により、予測が大きく外れるリスクも存在するため、過信は厳禁です。
また、 割引率の設定も主観が入りやすいため注意が必要です。リスク評価の難しさから、適切な数値設定に苦心するケースが多く見られます。
さらに、 非財務的な価値が反映されにくい点も課題です。従業員の技術力や企業文化、取引先との関係性など、数値化が難しい要素は評価に含めることが困難です。特に、老舗企業やブランド価値の高い企業では、こうした点が大きな課題と言えるでしょう。
DCF法による評価を成功させるには、いくつかの工夫が必要です。将来予測は複数のシナリオを用意し、最悪期と最良期の幅を持たせた評価を心がけましょう。
また、割引率設定では、同業他社の実績値や業界標準を参考にし、客観性を担保するのがおすすめです。ただし、一度設定した数値も定期的な見直しが推奨されます。特に、事業環境の変化が激しい業界では、年1回程度の見直しが望ましいでしょう。
DCF法は、将来キャッシュフローの現在価値算出により、事業価値を評価する手法です。計算の複雑さや予測の難しさはありますが、事業承継やM&A、投資判断など様々な場面で活用されています。経営者としては、自社の特性や業界動向を踏まえた現実的な予測と、適切な割引率設定により、より高い評価を目指してみるのも良いでしょう。その際は、より精度を高めるために、他の評価手法との併用も視野に入れてみるのがおすすめです。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。