現在掲載中の企業73件
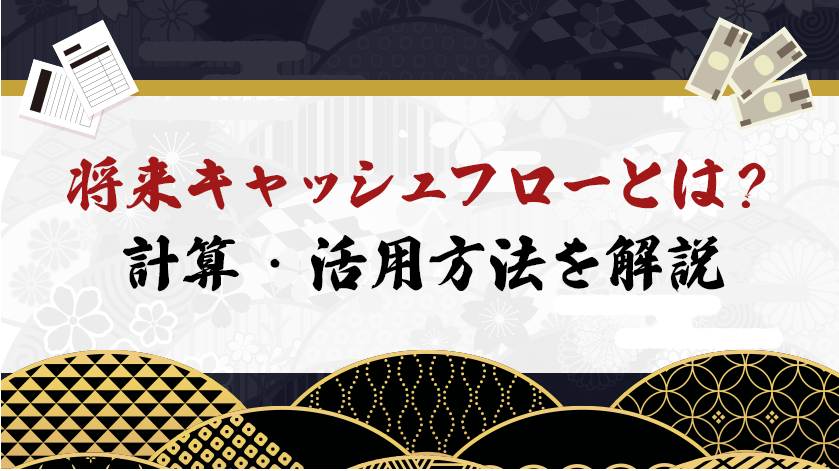
企業が安定した経営を行うには、将来キャッシュフローという視点が不可欠です。売上や利益が伸びていても、実際の資金が足りず黒字倒産に陥る事例は珍しくありません。逆に赤字計上でも将来の入金が明確なら、事業を継続する道は残されているでしょう。
本記事では、将来キャッシュフローとは何か、その計算方法や経営への活用方法を分かりやすく解説します。

まずは将来キャッシュフローがどういったものかを理解する必要があります。その前提となるキャッシュフローについても触れていきますので、ぜひ参考にしてください。
キャッシュフローは文字どおり「現金の流れ」を指し、売掛金や在庫といった勘定科目の動きとは別物です。例えば、帳簿上は利益が出ていても、実際には入金が遅れて資金繰りが苦しくなるケースがあり、それが「黒字倒産」の一因となります。
経営者としては、売上や利益だけでなく、いつ現金が入ってくるかを意識しなければなりません。その将来的な動きを見える化したのが将来キャッシュフローです。
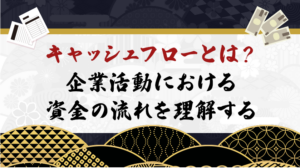
将来キャッシュフローとは、企業が今後受け取る現金と支出のタイミングを数値化したものです。
利益とは異なり、「実際の資金繰り」に焦点を当てている点が特徴と言えます。
会計上は黒字でも、売掛金が増えて現金が手元にない状況が続けば、経営が回らなくなる恐れがあります。そうした危機を防ぐためにも、将来キャッシュフローを予測し、入出金のズレを見極めることが大切です。
企業の価値は、将来的に生み出すキャッシュフローの現在価値に基づいて評価されることがあります。なぜなら、投資家や経営者は、将来キャッシュフローを予測し、事業の収益性や投資のリスクを判断しているからです。
また将来キャッシュフローの見通しは、企業が成長戦略を立てる際の基礎です。資金調達や設備投資の計画を立てる際には、キャッシュフローの安定性を考慮する必要があります。
なお、キャッシュフローと利益は同じものではありません。
利益は発生主義会計に基づき、売上や費用を認識しますが、キャッシュフローは現金主義会計に基づき、実際の現金の流れを示します。
そのため、利益が出ていても資金不足に陥ることがあるため、キャッシュフロー管理が重要になります。

経営を考えるうえでは、将来のお金と現在のお金が同じ価値を持たない点を理解する必要があります。これは「時間価値」という考え方で、投資によって将来得られる収益を、現在の価値に変換して評価することが経営判断でも求められます。
お金には運用や利息といった投資機会が存在します。もし利回り5%で運用できるなら、現在の100万円は1年後に105万円になります。今手元にある資金を事業に投じれば、さらに大きな利益を生むかもしれません。
将来的なリスクやインフレの影響で、受け取る金額そのものが減る可能性も無視できません。そうした不確実性を数値化するために、将来のキャッシュフローを割り引いて「現在価値」を算出します。
現在手元にお金がある場合と、将来にならないと受け取れない場合とでは、明らかに行動の自由度が変わるはずです。将来の100万円より、いまの100万円を優先的に考える人が多いのは、いつでもそのお金を使ったり増やしたりできるからという理由が大きいでしょう。
また、将来には景気変動や取引先の信用リスクなど、さまざまな不確定要素が潜んでいます。もしインフレが進めば将来のお金の価値は下がるかもしれません。そうしたリスクを織り込んだうえで、将来の受取額を現在の視点で評価する必要があるのです。
将来キャッシュフローを現在価値に計算し直すとき、どの程度の割引率を用いるかはとても重要です。おおまかには「リスクフリーレート」と「 リスクプレミアム」を足し合わせて算定し、さらに企業や業界ごとのリスクを反映して決定します。
例えば、国債の利回りを参考にしたうえで、事業の不確実性や財務体質などを評価し、どれくらい上乗せするかを考えます。中小企業は大企業に比べてリスクが高めと判断されるため、割引率を高めに設定されがちな点に留意しましょう。

将来キャッシュフローを予測する際は、「直接法」と「間接法」という二つの方法がよく使われます。企業の規模や目的によって適切な手法は変わりますが、管理用途や説明用途など、どちらの場合にも自身が把握している会計数値と矛盾しないよう注意が必要です。
直接法は、将来の収入と支出を細かく積み上げて予測します。
具体的には、売上収入、仕入支出、人件費支出など、実際の入出金を時系列で列挙し、月ごとのキャッシュフローを算出する方法です。
経験則や季節変動などを組み込みやすく、小規模事業者にとっては直感的にわかりやすい手段でしょう。
間接法は、損益計算書の利益ベースから減価償却費や運転資本の増減分を調整してキャッシュフローを導きます。
税理士や公認会計士と連携しやすく、損益計算書や貸借対照表をベースに数字を組み立てるため、比較的大きな企業の管理部門などでよく採用される手法です。
直接法では、売上予測や経費予測をどこまで現実的に設定するかが重要です。過度に楽観的な見通しを立てれば、実際の資金ショートを見落とすリスクが高まるでしょう。
間接法でも、特殊な会計処理や一時的な要因で数値が歪む場合があるため、単純に財務諸表の数字を機械的に当てはめるのではなく、背景事情を考慮しながら調整する必要があります。

将来キャッシュフローは企業価値評価や投資判断、そして日々の事業計画策定にまで広く活用できる指標です。どの場面でも、未来のお金の動きを現実的に予測し、その結果を分かりやすい形で示すことが、経営者の選択をサポートするうえで極めて大切です。
DCF法(割引キャッシュフロー法)は、今後得られるお金の流れを現在の価値に換算し、事業全体の評価額を見積もります。事業承継や会社売却の場面では、業界動向や不確実性を考慮しつつ、複数のシナリオを想定して判断することが不可欠です。
特に成長企業は数値の変動幅が大きいため、慎重な算定で後継者・投資家の信頼を得られるでしょう。
設備投資や新規事業への投資判断には、将来キャッシュフローが投資額をいつ回収できるかで左右されます。初期費用だけでなく、運転資金や在庫増も考慮して資金需要を洗い出すことが重要です。
イニシャルコストや維持費を含めた見通しがないまま資金を投じると、成長機会を活かしきれないばかりか、資金繰りの悪化で事業を危うくする恐れもあります。見通しを根拠に計画的な投資を行えば、将来の利益と安全性を高められるでしょう。
将来キャッシュフローは、事業計画を立てる際にも大きな役割を担います。月ごとの入出金を具体的に把握しておけば、必要な運転資金や借入金の返済計画をスムーズに立てられるでしょう。
ただし、事業計画は定期的な見直しが欠かせません。予測と実績の差を分析をし、計画の精度を上げていくことで、経営判断がより正確になります。変化の激しい経営環境に対応するためにも、柔軟に修正していきましょう。
将来キャッシュフローをしっかり把握することは、単なる数字合わせ以上の意味を持ちます。黒字倒産や資金不足を防ぎ、安定した経営基盤を築くための羅針盤とも言えます。適切な予測と活用により、より確かな経営判断が可能となるでしょう。
利益計上だけを見て安心せず、現金が手元に入るタイミングを見定めることが本当の意味での資金繰り管理です。数字に対する苦手意識があっても、基本的な考え方さえ理解すれば十分に対応できます。ぜひ一度、自社の将来キャッシュフローを見直してみてください。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。