現在掲載中の企業73件
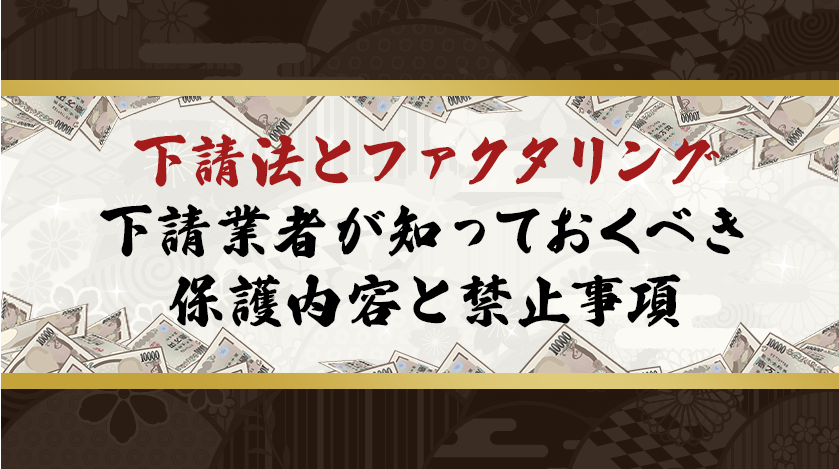
経営資金の確保に悩む下請業者にとって、ファクタリング(売掛債権買取)は有力な資金調達手段となります。また、事業者との関係においても、ファクタリング利用時に下請法による保護が受けられることをご存知でしょうか。本記事では、下請業者が債権譲渡後も法的保護を受けられることや、トラブル発生時の具体的な対処法について分かりやすく解説します。実務上の注意点や、経営者の視点から見た対策についても見ていきましょう。

下請法とは、下請業者と事業者の取引を適正化して、下請業者の利益を守る目的で制定された法律です。事業者による不当な取引条件や、支払遅延から中小企業を保護するための法律です。以下では、下請法の概要や適用範囲などについて解説します。
下請法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」であり、中小企業に配慮した内容の法律となっています。事業者による支払遅延や不当な代金減額から下請業者を守ることを目的として制定されました。
下請法によると、事業者には発注書面の交付を義務付けており、支払期限も納品から60日以内と定められています。そのため業務を請け負う中小企業からすると、取引条件が明確化されて、支払遅延のリスクが低減されるメリットがあります。
近年では、働き方改革関連法の施行に伴い、中小企業などの下請事業者への支払額アップを考慮した取引価格の見直しも求められているため、下請法は価格交渉の際の重要な根拠として活用することも可能です。
下請法が適用される取引は、事業者と下請事業者の資本金規模によって決まります。
製造委託・修理委託の場合、事業者が資本金3億円超で下請事業者が3億円以下、もしくは事業者が資本金1千万円超3億円以下で、下請事業者が1千万円以下という区分となっています。
対象となる取引には、部品製造や製品の修理、プログラムの作成、運送、物品の保管など幅広い業務が含まれており、建設業における下請工事や、設備の据付工事なども法律の保護対象です。
情報成果物作成委託では、プログラム開発やデザイン制作なども保護対象に含まれ、デジタル化が進む現代のビジネスモデルにも対応しています。
下請法では、事業者に発注時において注文書の交付が義務付けられています。注文書には発注日、商品の内容、納期、代金額、支払期日などを明記しなければなりません。
支払期限については、下請代金の支払遅延を防止する観点から、原則として納品から60日以内と定められています。事業者による一方的な支払期限の延長や、取引条件の変更は認められません。
また、実務上重要なポイントとしては、発注書面の保存期間は2年間と定められている点に注意しましょう。

事業資金を確保するためにファクタリングを利用する場合でも、下請法による保護は継続されます。債権譲渡後も事業者による不当な行為は禁止されており、下請業者の権利は守られます。以下では、このような法的保護の仕組みについても詳しく見ていきましょう。
売掛債権をファクタリング会社に譲渡した後も、下請法による保護は有効です。
事業者は支払期限を守る義務があり、支払遅延や減額は違法となります。
また、ファクタリングの利用を理由に取引を停止したり、嫌がらせをしたりする行為も違法です。なぜなら、債権譲渡は下請業者の正当な権利として認められているからです。
さらに、債権譲渡禁止特約が付されている場合でも、下請事業者の資金繰りを不当に制限するものとして、その効力が否定される可能性があります。
事業者による具体的な禁止行為には、支払遅延や受領拒否、減額などがあります。債権譲渡を理由とした取引停止や発注減少といった行為も認められていません。
また、不当な買いたたきや不要なサービスの強制など、優越的地位を利用した行為も禁止されています。下請業者に対して、債権譲渡を理由に不利益な取扱いをすることは許されません。
実務上よく見られる事例としては、口頭での発注や事後的な単価の引き下げ要請がありますが、このような行為も違法となります。
ファクタリングを利用する際は、取引の証拠として契約書の作成が重要です。事業者との取引条件や支払条件、債権譲渡に関する合意事項を書面で残しておきましょう。
また、取引記録は最低5年間保管する必要があります。そのため発注書や請求書、納品書、支払記録などを保管しておけば、トラブル発生時の証拠として活用できるでしょう。

事業者とのトラブルは、事業継続に大きな影響を及ぼす可能性があります。トラブルが発生した際の具体的な対処方法を理解しておけば、適切な対応が可能となります。
具体的には以下のような点を、押さえておくべきポイントとして詳しく解説します。
公正取引委員会では、下請法に関する相談窓口を設置しています。
電話やメールでの相談が可能で、専門の相談員が対応します。窓口では匿名での相談も受け付けており、気軽に利用できる体制が整っているのでご安心ください。
また、中小企業庁の「下請かけこみ寺」も相談窓口として活用できます。
全国48ヶ所に相談窓口があり、弁護士による無料相談も利用可能です。
近年ではオンラインでの相談受付も開始され、より利用しやすい環境が整備されています。
トラブル発生時に備えて、契約書や請求書、発注書、支払記録などの証拠書類を適切に保管する必要があります。日付入りの記録や、メールのやり取りなども重要な証拠となりますので、残しておきましょう。
また、電子データは定期的にバックアップを取り、紙の書類はスキャンして電子化するなど複数の方法で記録を残すことをおすすめします。タイムスタンプ(電子署名)付きの電子データ保存も有効な証拠として認められていますので、この方法で残しておくのもいいでしょう。
その他にも、取引の重要性に応じて、公的機関による認証サービスの利用も視野に入れておくとより安心です。記録管理の担当者を決めておき、定期的な確認作業を行う方法も役立つでしょう。
法律の専門家である弁護士への相談は、トラブルが深刻化する前に検討しましょう。初期の段階で適切なアドバイスを得ておけば、問題の拡大を防ぐことができます。
また、心配な弁護士への相談費用は、法テラスの無料法律相談や中小企業向けの法律相談制度を利用することで抑えられます。経営者向けの顧問弁護士契約についても、月額1万円程度から提供されており、定期的な法律相談が可能です。
さらに、商工会議所や信用保証協会などの機関も、専門家紹介サービスを提供しています。会計士や社会保険労務士など、他の専門家との連携も視野に入れた総合的な経営相談体制を整えることで、より強固な経営基盤が築けるでしょう。
このように事業規模に応じて、複数の専門家に相談できる体制を整えるのがおすすめです。
下請法は、債権譲渡後も下請業者を保護する法律です。ファクタリングを利用する際も法的保護は継続され、事業者による不当な行為は禁止されるのでご安心ください。
そのため、ファクタリング利用時は取引記録の適切な管理を心がけて、トラブル発生時には行政機関の相談窓口や専門家への相談を積極的に活用しましょう。日頃からの備えと適切な対応が事業の安定的な継続につながります。
ファクタリングの 達人編集部
自らの経験に基づいた、ファクタリングや与信管理に関する豊富な実績を持ち、これまでに数百社の取引をサポート。
当メディアでは企業の資金繰りに役立つ情報発信を行うとともに、中小企業向けにファクタリングのアドバイザリーサービスも提供しています。